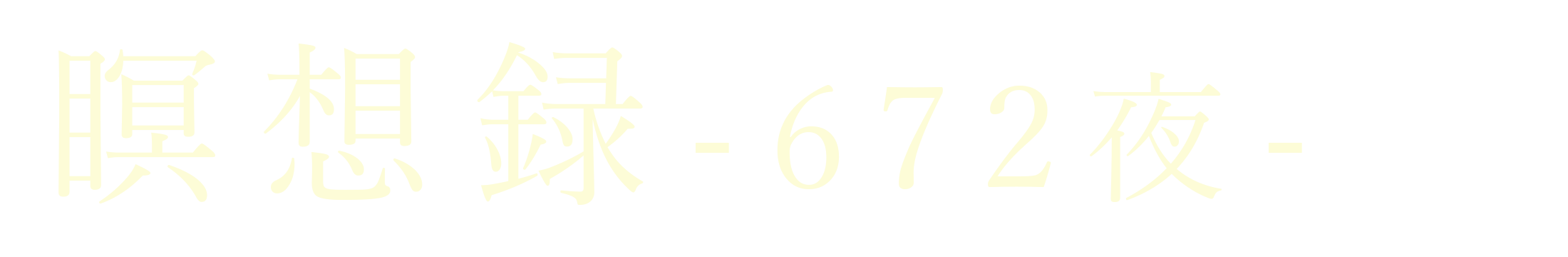”静かに”(瞑想)したいと思います。しかし、静かにしたくない自分のことも認めます。まだ概念の中で遊びたいのだと思いました。概念が次第に真実に溶けて行き、いつしかそれそのものとして生きることが出来るのだと大きな勘違いをしていました。知識を得たい、知りたいとは、この私が(人生を)動かしたいという現れなのだとも思いました。
静かにしたくない暴れと、自分は別である。しばらくの間、静かにしていることは難しいだろう。それを無理に静かにさせることは、病気や狂気のようなものを引き起こす原因になる。静かにしようと思って瞑想するとき、静かにできない場合、重要なことは、静かにできなくていいことを知ることである。「私は静かにできない」などの想念と戯れることが一番の間違いである。私と、静かにできない肉の衝動は、別である。様々な想念や概念であれ、このような衝動であれ、「次第に真実に溶けて行き、いつしかそれそのものとして生きることが出来る」というのは勘違いではなく、事実である。ここが難しいポイントであるかもしれないから取り上げさせてもらった。
例えば今、私が自我意識に戻されて、本物から切り離され、しかしどうすればよいかは覚えているとしよう。私は瞑想するだろう。しかし静かにはできない。私という器に本物がまだ入ってきていないからである。本物が入れるようになるまで、しばらくの、あるいは数年の瞑想が必要だということを思い出すだろう。そして私は、静かにできない自分であることに、一切抵抗しないだろう。なんであれ、それでいいことを知っているだろう。あれはダメでこれは良いという判断には騙されないだろう。静かにできないから瞑想できない人、ではない。誰も最初は瞑想できない。自我は瞑想の対義語である。それは永遠に瞑想できない存在である。そして、私は自我ではない。このことを私は覚えているだろう。したがって、静かにできない肉の衝動があっても、それが問題になることはない。それでいい。ただし、静かにできなくても、可能な時間、毎日瞑想を続けるだろう。しかも、やがて静かになるという望みから瞑想するのではなく、そのような想念とも関わらないようにして、ただ静かにしているだろう。そのうち、心地よくなってくるはずである。すると、その心地よさの方が好きになり、心地よい当のものへの集中が趣味になるだろう。ほとんど病みつきになるだろう。このようにして自我と真我は融合を開始し、なにもかも、次第に真実に溶けていくだろう。
要点を言う。何であれ、それでいいと思うことである。つまりは無抵抗だが、これも最初からはできない。なぜ私が、あれは好きでこれは嫌いというものがないのか内側を見るとき、秘教徒が相反する対をなすもの、と呼ぶものを中央で統一してしまっているから、その中道の細い小道の最奥におられる「蓮華の中の宝珠」にとどまっているから、抵抗しようがなく、充足しており、この世の好き嫌いは私には関係ないからである。ラマナ・マハリシ的に言えば、木陰で涼んでいた者が、わざわざ出ていって暑い目に遭うようなことをしないということである。となれば、何であれ、それでいいとか、どちらでもいいとか、好き嫌いから自由で、選択に関して無関心であるというのは、融合しているからということになる。であれば、このようなことが起こる前、私は何をしていたのであろうか。つまり自我として、静かにできなかった時期を、どう過ごしてきて、いつのまにか融合していたのであろうか。
記憶を辿ろうとする。融合後は、覚えていないことを思い出すために記憶を辿ろうとすることが非常に難しくなる。思い出そうと試みることは、木陰から出ることを意味するからである。木陰は永遠なる現在であり、神である。記憶は、神の対義語、つまりほとんど悪魔である。したがって、記憶を辿ろうとしても、引き戻すような作用つまり力の方が強いため、いわゆる過去を思い出さない習慣がつきすぎて、記憶が薄れてしまったり、不確かなものになったりするのである。思い出せないし、思い出させない作用の方が強すぎると言っても、これは全く答えにならず、ここまで読んだ人に不満をもたらすだろうが、私は記憶とは無関係であるとしか言いようがない。
理解できるのは、神が器に入る前、つまり瞑想できない時期、自我意識である時期、頑張って、こらえて、耐えて、諦めて、努力にはなるが、その道のみを必死に真剣に求めねばならないということになる。これは、日頃の私の話と逆ではないだろうか。私は無努力の道を日頃は説くが、それはじっさい正しいものの、融合後の状態から正しさを説いているだけであって、その前はできないものであり、私が思っていたほどの良い教えではないかもしれないとうことになる。質問者の形をとったもう一人の神に、私は教え方の間違いを教えられたといって差し支えないだろう。ラマナ・マハリシがクリシュナムルティについて言及したとき、「彼は到達したから言えるのであり、その前ではありません」と言ったが、私は深くここから学ばねばならない。
初めてクリシュナムルティを知って読んでいたとき、このインド人は、自分の状態を語っているだけで、何の役にも立たないと思った記憶は覚えている。また、それを記事に書いた覚えもある。次のような書き方をしたと思う。当時、どこまでの意識に到達していたかは分からないが、「クリシュナムルティは上から降りてこず、ラマナ・マハリシは降りて語った」と書いた。つまり、「私は誰か」とか、自我ができそうなことを教えたと言ったのである。
とはいえ、確かに私は自我で色々試しはした。そしてすべて失敗するものであることを学び、自我にできることは何もないことを理解してきた。専門的に言えば、エネルギーとフォースを識別できるようになっていった。言い換えれば、神の意志と個人の自由意志の違いを区別できるようになり、神の意志だけが本物、実在であり、他は錯覚であることを理解してきた。おそらく私は、このような過程で、自然と抗わなくなったのだろう。自我の力(フォース)では、神(エネルギー)とは一致できないことは自明である。錯覚を使って本物に至ることはなく、本物が来て錯覚が去るというのが事実であり、それは闇と光のようなこの世の象徴でも言えることである。光が来ないと闇は去らない。闇で闇は追い払えない。自我で自我は追い払えない。真我だけが自我を追い払う。
瞑想とは、少しずつ、光を器に引き入れる作用をもたらすものである。条件づける低い波動を、光は高みに引き上げてくれる。それは意識の変化として知覚される。よって、意識の上がり下がりを繰り返しているうちに、人は、低い波動と高い波動を識別するようになり、低い波動とは関わらず、高い波動だけと共に在りたいと願うようになる。最初は日に一二時間でよかった瞑想も、終盤は永続的な瞑想になる。これに関して一つ二つ引用できるだろう。
朝の瞑想で達成した高い調子にできるだけ近い意識を毎日一日中毎時間維持するように試みるべきである。自分自身を、分離したパーソナリティーではなく、魂と考えようと決意することが前提である。後に魂がもっと支配力を握るようになったとき、グループのためにならない関心、欲求、目的、願望を全く抱かずに、自分自身をグループの一部と見なす能力も必要になるだろう。また、低位の波動への逆戻りを防ぐために、一日のあらゆる時間、絶えず注意を払うことも必要である。引き摺り下ろそうとする低位我と絶えず戦わなければならない。高位の波動を維持するための絶え間ない戦いである。そして、これはあなた方に印象づけたいと思っている点であるが、目指すべきものは、一日中瞑想する習慣を発達させ、高位の意識をもって生活し、この意識を安定させることである。その結果、低位マインド、欲求、肉体エレメンタルは養分の欠如によって萎縮して飢え死にし、三重の低位性質は魂が人類の救済のために世界に接触するための単なる道具になる。
アリス・ベイリー「秘教瞑想に関する手紙 」p.175
これは、融合が多少確立され出した後の者への教えであり、初期段階では以下の教えを重要視すべきである。
学ぶ人は、着実で静かな、感情的ではない活動に取り組むようにし、学習や瞑想に何時間も連続して没頭することは慎みなさい。諸体はまだ必要な緊張に耐えることができず、自分自身に損傷を及ぼすだけである。日常の義務や奉仕に追い立てられながらも、自分が本来誰であり、自分の目的と目標が何であるかを思い起こしつつ、正常で多忙な生活を送るようにしなさい。十五分という長さから始め、決して四十分を超えないよう、毎朝規則正しく瞑想しなさい。奉仕に専念し、自分自身のサイキック的な発達に関心を集中させないようにしなさい。
ハイラーキーの出現上 p.36
異なる段階の者を想定して教えているため、上と下の引用は逆のことを言って部分がある。静かにできない時期は、下の教えが事実である。長時間瞑想は病気や狂気を引き起こす。しかしながら、瞑想を正しく続けるならば、やがて瞑想状態でないことが苦痛になり始めるだろう。高位の意識のみが自然であり、それ以外の不自然がすべて苦痛になったとき、24時間瞑想は永遠の喜びの秘訣になるだろう。
以上をまとめる。私から見れば、あらゆる努力は霊の道に反している。つまりクリシュナムルティと同意見である。しかし、ラマナ・マハリシが指摘するように、「以前はできなかっただろう」ということである。静かにできない時期や、無努力の自然な意識ではなかった時期があっただろうということである。だから、例えば誰かが熱心に瞑想しているのを見るとき、私には間違った瞑想に見える。自我で瞑想しているからやめるようにと、その意味を伝えたくなる。しかし、本物が入る前の意識ならば、私は自我である。したがって、自我以外のことができないということになる。だから、自我を通り抜けた後の者の教えは、自我には適用できないことになり、かつての私がクリシュナムルティに失望したように、「このインド人の話は役に立たない」という結論に到達する。すると思い出される。私もまた、すべての本に失望してきたと。がっかりしてきたのだと。だから背を向け、己に向かったのではあるまいか。己で見出すしかないと、清々しい気持ちになったのではあるまいか。書物の内容に縛られず、空にして、すでに在る私へと向かったのではあるまいか。書物に失望するのと同じだけ、自我の試みにも失望してきたがゆえ、徐々に何もしなくなったのではないのか。このようにして、「次第に真実に溶けて行き、いつしかそれそのものとして生きることが出来る」ようになったのではあるまいか。――
私は今回、質問者によって学びを得た。それが正しいにしても、正しさと一体化する前は、正しさができないものであり、正しく在ろうと努力することしかできない。それは依然として間違っているが、自我の努力という間違いの経験を通してしか、静かにならいものかもしれないし、実際に私も間違いを通して間違いを理解し、本物に委ね生きることが可能になり、それそのものになったのではあるまいか。であるならば、人の失敗、苦しみ、絶望というものは、やはり、祝福でしかない。