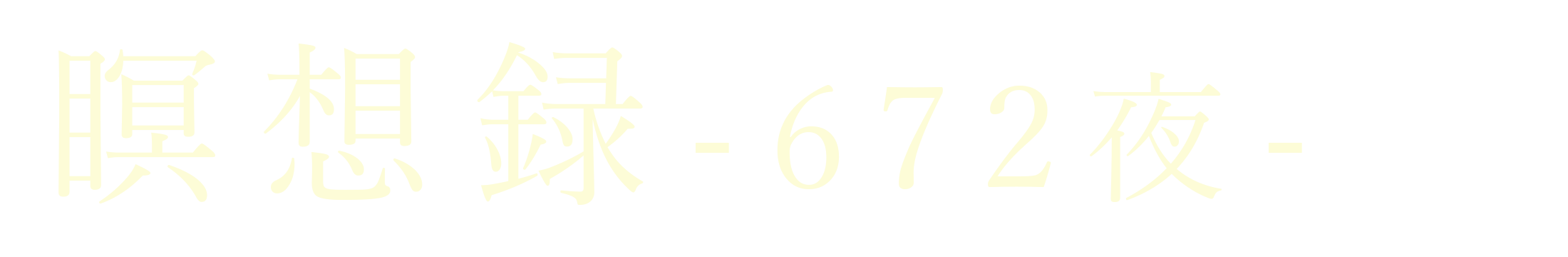瞑想が魂との接触を確立するための方法であると考えられることが非常に多いものの、この接触が、マインドの内的な思索的態度、奉仕と愛他に捧げられた人生、低位性質を魂の真の経路にするよう訓練するという決意によって、かなりの頻度で起こるということを、人々はしばしば忘れている。
アリス・ベイリー「新時代の弟子道4」p.170
奉仕と愛他に捧げられた人生は、低位性質を魂の真の経路にするための優れた訓練の一つであり、それが首尾よく進行するためにはマインドの内的な思索的態度が必要である、と言い換えることもできるだろう。奉仕と愛他に捧げられた人生は、魂と融合した弟子たちにおいては通常の生き方である。それ以前においては努力になる。そしてその努力の背後には、霊的な達成を目指すという個人的な動機が常に存在しており、純粋な奉仕からは程遠いということを、マインドの内的な思索的態度は教えるものである。これはある程度まで仕方のないことであるが、より純粋な奉仕と愛他を達成するための思索として、以下の引用は役に立つであろう。
愛ある理解は、その持ち主が自分自身ではなく他の人々と同一化しているために生まれるものである。このような人は「私は他の人々と同一化している」という態度はとらない。また、自分が他の人々と同一化しているかどうかを見守りながら、同時に自分自身や自分の反応に集中し、……より幸せに仕事をこなし、幸せな意識になるために同一化を達成しようと努めることもない。そうではなく、「私の兄弟は何を感じ、何を考えているのか」と言う。というのも、自分の感覚や思考よりも兄弟の幸福に関心があり、手助けし、刺激し、知恵を持って愛するために状況を見極めることに没頭しているからである。
「新時代の弟子道4」p.276
このような態度が起こるのは、実際には、すでにその弟子が高位の意識を達成しているからにすぎない。つまり、自分はもはや魂として愛と美と喜びに生き、どれだけ賛美してもしきれないほど神の大愛に包まれているゆえ、自分のことがもはや目に入らないだけである。しかしながら、達成していないときは、愛というものは彼にとって完全に未知であり、彼が想像しているものとは完全に異なるものであるため、愛において他の兄弟姉妹のことを考えることはできず、その余裕もなく、自身の苦悩に対処することだけでも精一杯である。その状態では、あまりにも苦しいため、他人の前で笑顔を作ることすら至難であり、ましてや苦しみながら、自身の苦しみを堪えながら、奉仕や愛他を実践しようとすることは、あまりにも困難なことに思われるものである。
私が以前にそのような葛藤を抱えていた頃、あるとき、方法を発見した。もしくは、愛という波動にオーバーシャドーされないのがなぜかを理解した。つまり、自分のことを考えれば考えるほど、愛という波動は流入できず、逆に他人のことを真に思いやり、辛い環境の人、苦しい状態の人のことを想い、なんとかその助けになりたいと願う心が、自身の苦悩に打ちひしがれている心の中にもわずかながら存在することを発見した。それは良心に近いものである。したがって、自身ではなく、自身に内在する良心に焦点を当て直し、その思いやりや労りの心に集中し、自分という内側ではなく、他人という外側にだけ心を開くならば、私にも愛という高次の意識がその瞬間に開かれることを知ったのである。それは魂の愛様相と一体化したときに開示される意識状態である。これには驚いた。つまり、自分で元から存在する愛を封じ込めていたことを知ったのである。
愛が解放する主要なテクニックであると言われるのはそのためである。私は、他人を愛せないと思っていた。しばしば苛立ち、絶対に許せない多くの人が存在していた。次に私は、愛というものは自我から発出するものではなく、すでに内在しており、そのような「高所」から降りてくる魂由来のものであることを知り、完全に愛の虜になった。つまり言いたいのは、このような考え方の逆転が誰にでも実は可能であり、不可能に思われている最中にも実際には可能であり、ほとんど我々の決断にかかっているということである。「私に苦しんでいる他人を思いやる心はあるか」と最初に問うのである。すると在るはずである。見つけたならば、その感覚を、外に向かって放射するように心象化することである。ハートで愛を感じるかもしれないが、放射の際は、眉間に座する魂の位置から、ハートとアジュナを心象化でもかまわないから一体化させ、我そのものがハートの中心であり愛の中心であるという感覚から、特定の個人でも、あるいは森羅万象にでもかまわないから、それを解き放つのである。すぐにそれが心地よいことを発見するだろう。愛したとき、神に愛され、神の愛がオーバーシャドーし、苦悩がたちまち癒やされたことを知るだろう。
言いたいのはそれだけである。本日は他にも記事を書いているため、この主題に関してはおそらくこれだけで十分であり、あとは実践してくれる人が数人いれば十分である。