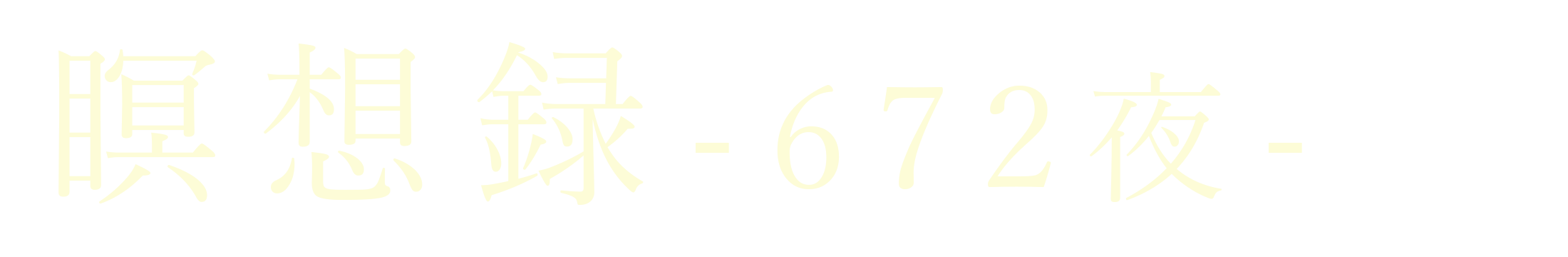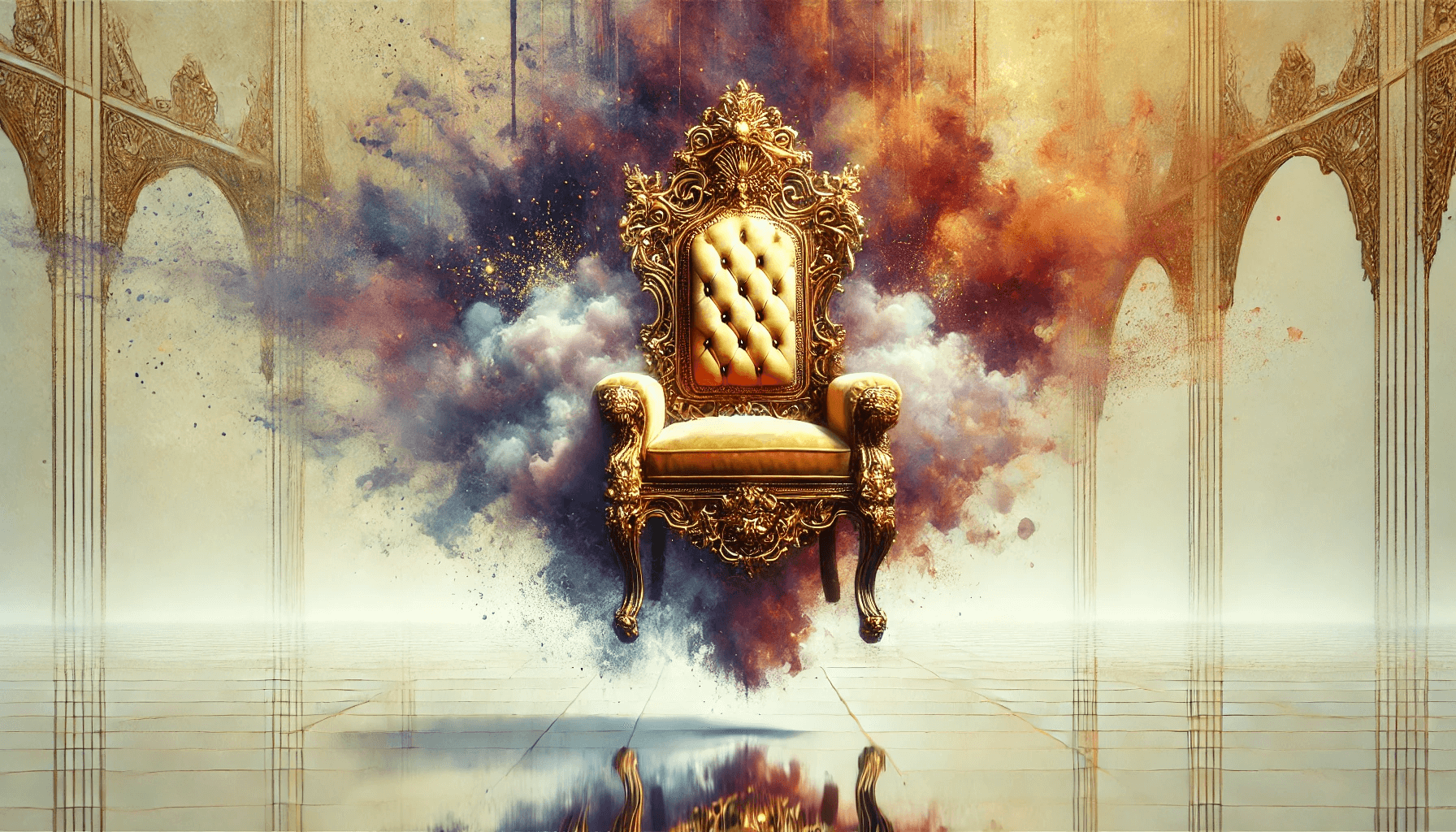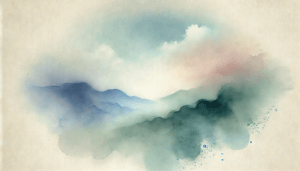行為者感覚の消失
融合した者は、いわゆる「行為」に対して、ただ気づいているだけである。対照的に、融合以前の探求者は、常に「それをしているのは自分だ」という思考の中に生きている。彼の注意は行為そのものよりも、行為する自分という観念に吸い取られている。
魂として在る者――そのような意識には、行為者という思考は存在しない。「自分」とは記憶や知識に根ざした思考の束であり、意識それ自体は、いかなる出来事とも無関係である。そのため、魂の意識には、行為も経験も出来事も存在しない。言い換えれば、活動的なマインドが生み出す「行為者感覚」は、完全に喪失している。その錯覚を、覚醒した意識が上から塗り替えている。
人間という痴呆
なぜ、このような転換が起こるのか。それは、「私」や「自分」という感覚そのものが、瞑想に熟練するにつれて、即座に苦痛として認識されるようになるからである。架空の想像と同一化するほど虚ろではいられなくなるのだ。遅鈍な呆けは、鋭敏な気づきに席を譲る。水面に差し込む月明かりのように、静かでありながら鮮烈な明晰さが全体を覆うのである。
したがって、「気づいていよう」とする探求者の努力は、高次の意識状態から逆算して行われる気づきの模倣でしかなく、根本的に仕組みが異なるものである。「気づいていようとすること」は、純粋な気づきに対する冒涜であり、抵抗である。気づこうとする人間のたくらみには、常にそれをしている「自分」という感覚が伴っている。しかし純粋な気づきは、そのような思考活動を支配し、統御するものである。それは人格に代表される分離思考を上回るものであり、したがって、目覚めにおいては気づかれないことやものは一切なくなる。これこそが、人間という仮構の意識、あるいは痴呆にも似た惰性からの根本的な切断である。
無知の連動
「痴呆」と喩えられたとき、人は「自分が否定された」と捉え、嫌な気持ちになり反発や反抗を覚える。「私の状態を痴呆呼ばわりした」という思考と、それに連なる邪悪な情緒にそのまま同一化するのである。この段階の意識は、思考や情緒と自分が関係していると思い込んでいる。このようにして非自己の感覚・想念が維持されるのである。
一方、融合が起きた意識にあっては、たとえ侮辱されたとしても、それに反応して立ち上がるのは愛である。侮辱するためには、怒りや憎しみといった情緒的思考に条件づけられる必要があるが、そのような無知の状態、気づきが介在できない、ただ反応に条件づけられるだけの意識に、哀れみと慈悲と愛という魂の反応が生じることに気づくだけである。
このような意味で、通常の人間は、やや無意識に近い生き方に縛られている。絶えず気づかないのである。腹が立てば、そのまま立腹を暴言や暴力で反射的に表現する。しかし、思考や情緒から切り離された意識は、怒りようがない。立腹は不可能である。それらは低い波動の表現だが、魂の意識はブッディのオーラの統御下にあり、低い波動との同一化が起こらない意識である。そこでは愛と一体性が支配原理となっており、傷つくことも苦しむことも起こりえない。ただ、気づきの根底に愛と喜びが静かに流れている。
導く力・意志
「どうやってその境地に至るのか」という思考に騙されないような成熟した意識だけが、思考を超えた領域に導かれうる。その導く力というものが、個人を限定する仕組みを破壊し、閉じ込める形態から意識を引きずり出すのである。したがって、思考や情緒と関わらないことは、「関わらないようにしよう」という行為とは関係がない。行為の背後には個人的な意志がある。個人的な意志とは、純粋な意志が、個人的なメカニズム――アストラル体やメンタル体に条件づけられた結果である。しかし、純粋な意志とのみ関わり交わる者は、つまりその意志で在る者は、個人をその限定から超越させる導きや作用それ自体なのである。
迷った自我意識は、導きや恩寵を期待する。彼らは、導きや恩寵というものが内在すること、ひいては自分自身であることを知らないのである。それらは、個人的な意志に歪曲される前の意志のことである。ゆえに、個人を可能にするメカニズムと関わらないとき、純粋な意志と意識の融合が生じ、それ自体が自然に超越へと導くのである。よって、個人的な意志に生きるか、その歪曲前の意志で在るかが、行為者感覚と存在感覚を分けるものだと言えるだろう。
気づきなき個人
以上をまとめると、「個人」は、「気づき」の介在がないことで生じ、維持されるものである。しかし「気づき」は、思考活動を超えたものであり、個人による気づこうとする努力とは異なるものである。これをはっきり説明する者があまりいないため、多くの探求者が自我という思考活動を通して気づこうとし、自身をマインドの領域に自ら縛りつけている。
まさにこのような、自我による偽の探求にこそ、自我は気づかねばならない。しかし結局のところ、自我は何かを「したい」ため、ほとんど全ての探求者は必ずこの事実から目を背ける。いかに、「探求」というものが自我の娯楽であり、真剣なものではないかが分かるだろう。しかし自我は見ないように逃げるため、気づかないふりをして、自分の欲求、自分の考え、自分の探求などの個人的なメカニズム(自我)へ奉仕するのである。この事実が真に見えるならば、理解されるならば、それは個人にはかりしれぬばかりの激震をもたらすものである。すべてが自作自演であることを知るとき、マインドは活動できなくなる。舞台の幕が下り、観客も演者もいなくなる。
ということは、終幕が起きないのは、いったい何ゆえなのであろうか?