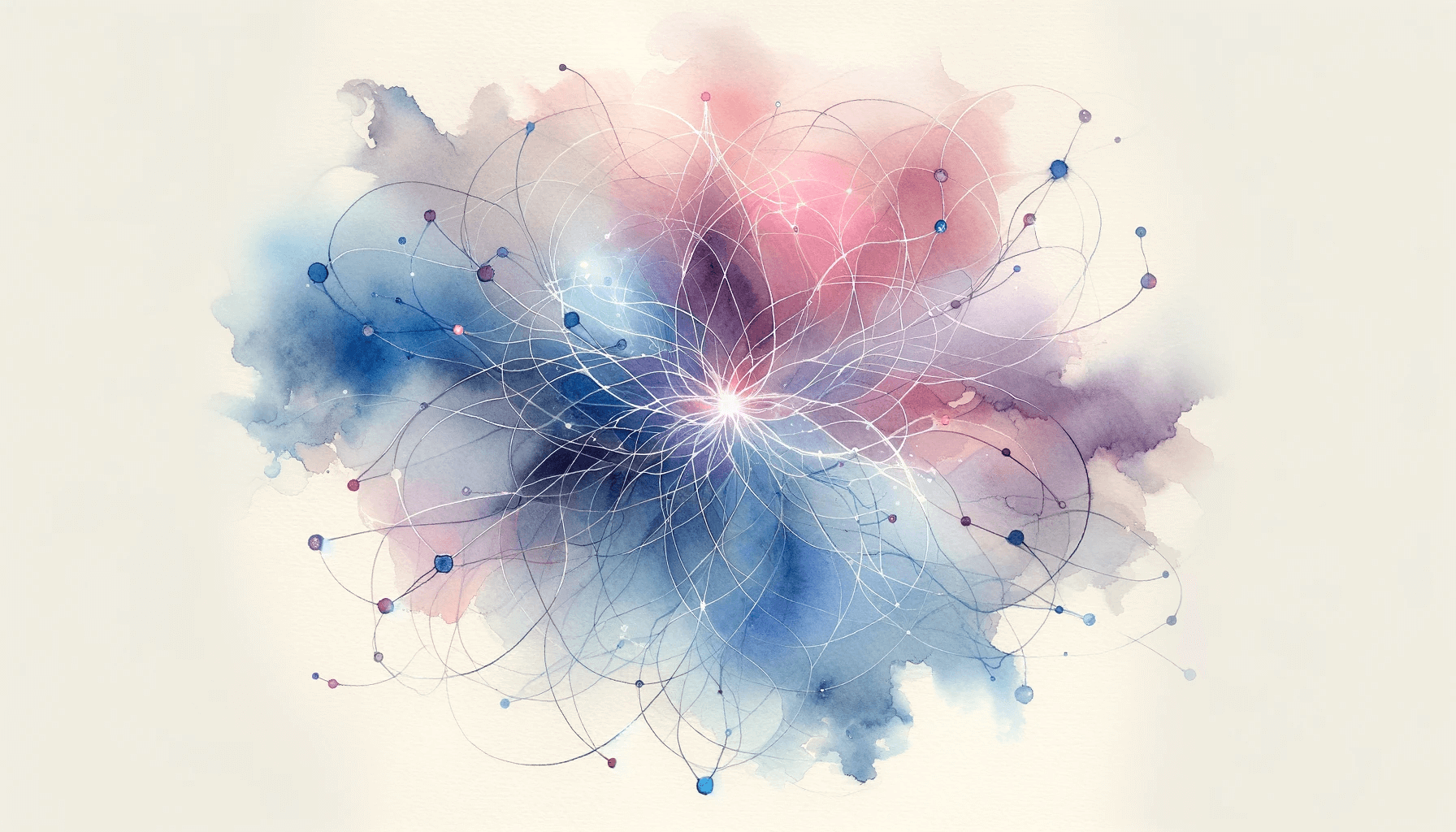何年瞑想しても、雑念に振り回されて集中できないという問題について。本質をつくために逆に質問する。なぜ集中しないといけないのか。なぜ雑念に振り回されてはいけないと思うのか。思っているのが個人だと分かるか。問題とみなしているのが自我であり、それが個人的な感想だということが分かるか。他人や書物に感化されて、霊的な何かを求めており、それを入手するために瞑想しようとしており、霊的な獲得のために雑念をどうにかしようとしている。これが初心者の自我瞑想である。これは瞑想ではない。何年かけてもどこへも導かない。
正しい態度を述べる。雑念があってもどうでもいい。なぜなら、雑念が真我に影響を与えることはないからである。個人が瞑想に失敗していようが、何の関係もない。四六時中、個人は瞑想の埒外に存在しており、彼の領域と真我の領域は交わってさえいない。自我はひとりでに騒いでいるが、真我は一度たりとも騒いだことがない。このように語ることで、焦点の合わせ方を少しでも理解してもらいたいという願いである。
例えば、ラマナ・マハリシの話の核心は、真我にとどまっていることである。そのために「私は誰か」と問わせることを考案した。この教えにはそもそも欠陥があることをマハリシは理解していたが、人々が沈黙の教えを理解しないため、比較的無意味ではあるが、他の態度よりはマシだという基準から考案した。これは方法論とみなされ、ひどく世界中の自我たちに好まれた。マハリシは沈黙の教えを強調していたという事実は忘れられ、人々は彼の教えの核心を、「私は誰か」にあると思いこんでいる。
沈黙の教えとは何なのか。先程述べた通り、自我はひとりでに騒いでいる。真我は自我と関係なく騒いでいない。真我が沈黙である。真我の影響力が沈黙の教えである。それは言葉が語るよりも多くをいちどきに教え、言葉が決してなしえないことを直接的に可能にさせる。マハリシは、真我にとどまることを教えたが、人々がそもそも真我を認識していないことが最大の問題である。どうして知らないものにとどまれるのか。マハリシが認めているように、真我の認識がまず最初である。秘教的に言えば、魂との接触が第一段階である。その結果、真我が個人に正しい態度を教えるのである。マハリシが外のグルではなくサッドグル(内なるグル)を強調していたのはこのためである。
「真我を知ることが第一だと言われても、私はなお自我だ」というのが自我の反応である。この反応から真我は離れている。真我とは文字通り真の私である。真の我々は、自我やマインドではない。我々が自我意識なのは、しかしマインドを自分だと思い込んでいるという、ただこれだけのためである。最初は致し方ない。だから誰もが自我で瞑想を始めるかもしれない。しかし次に、自我と真我は関係がないことを知らねばならない。いつまでも自我で瞑想していては進歩がない。このことを知り、自我として行うのではなく、自我はせいぜい観察の対象であるという考え方に切り替え、さらに進んで、自我と私(真我)は無関係であるという境地に落ち着く必要がある。このとき、自我に雑念が生じようが、いったい、何の関係が真我にあるだろうか。雑念を統御した末にようやく真我に至ることができるのではなく、諸体が波動的に調整され、そもそも存在している真我を知覚できるようになり、真我として我々は雑念から自由になるのである。
このような話が、本来なら、瞑想の基本として広まっているべきである。しかし人類は現状、アストラル界に偏極しており、欲望や恐怖が行動における支配要因である。霊的な話も例に漏れず、それは求める対象であり、あるいは恐れるものから逃れるための対象にすぎない。結果、人類の瞑想はアストラル瞑想である。この種の低位の波動から瞑想の真似事をするとき、我々はアストラル界の邪悪な存在に憑依されたり、大切な諸体を損傷させたりする。このような危険を放置したくはない。これまで確認されてきた真の教師方は、簡単に誰にでも瞑想をさせなかった。正しい人格、確固として真面目な人間性、揺らぐことのない善良な心、これらが瞑想の前提であると教えてきた。欲望で瞑想して、あえて危険な目に遭ってほしくない。意図的にチャクラを開花させようとしたり、クンダリーニの火を目覚めさせようとしたり、自分のために瞑想の効果を求めたり、これらの欲望に動かされる無知がもたらす災いを知らぬ者に、まだ瞑想をさせることはできない。人類を導く世の教師方は、瞑想を商売にするのではなく、お金を取ることで自分を助けるのでなく、瞑想で本当に兄弟姉妹を助けてほしい。助けられた者は、他の者を助けるだろう。火が燃え広がるように、愛が燃え広がるだろう。親切と善良さが、人類の次の喜びになるだろう。瞑想で与えられた力は、このような用途にのみ使われるだろう。なぜなら、神は善だからである。