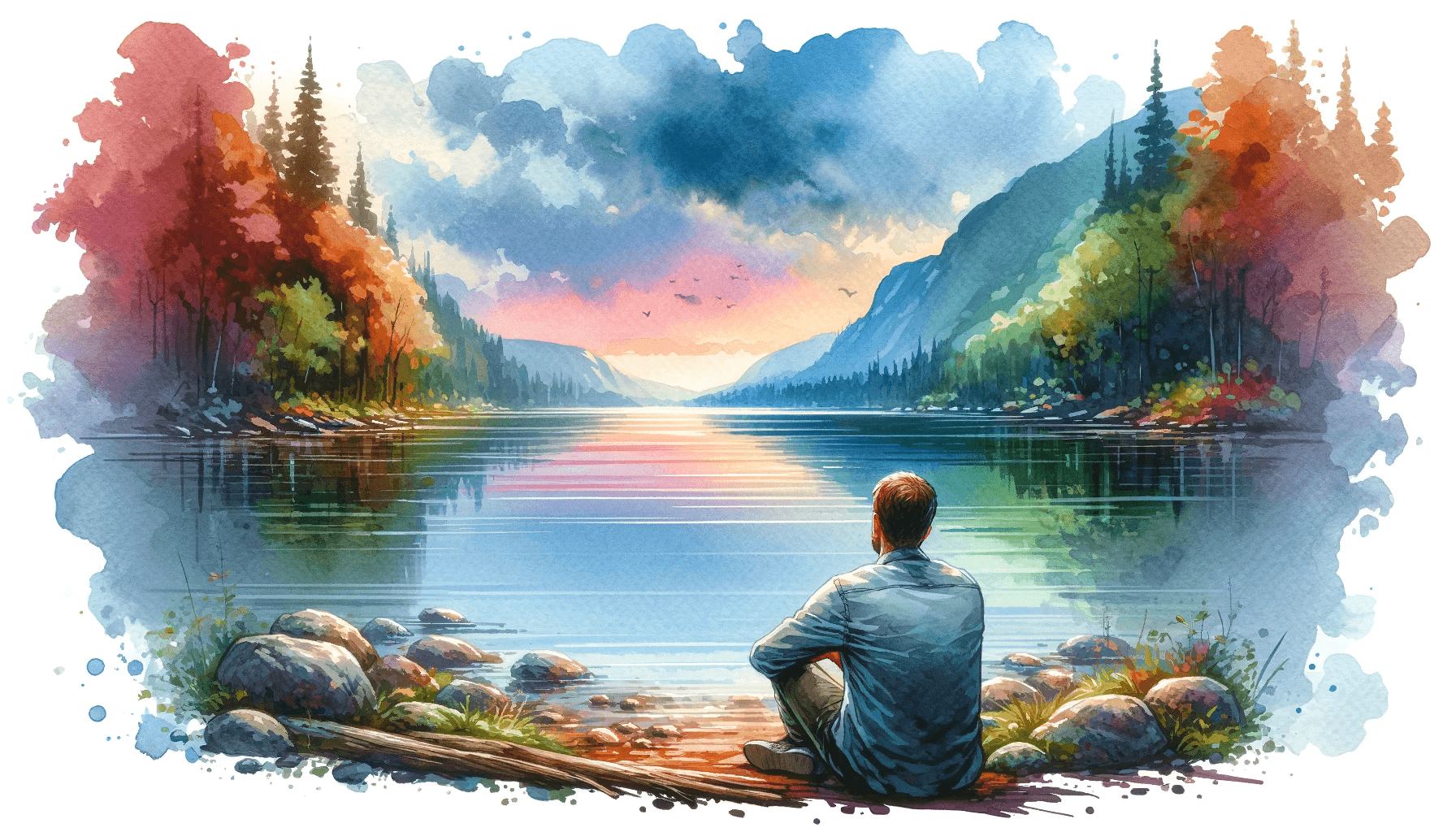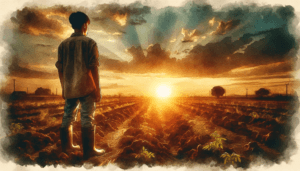この問いかけは次のことを示唆している。
- 何かをすることができるという錯覚。これは「自我としての私」と同一化しているときに生じるものである。つまり、行為が私に帰属するという傲慢である。彼は生命やエネルギーなしに指一本すら動かせないことを忘れている。
- 「自我としての私」という錯覚。これはアストラル体とメンタル体が統御されておらず、魂に整列していないときに生じるものである。感覚や情緒や想念と同一化することで、彼は一時的に真我のうえに騒音をかき鳴らし、騒音が自分だと思っている意識状態に閉じ込められている。これが自縛である。
- 何かすることで何か獲得されるという錯覚。これは何もしないときに無窮なるものの存在が知覚されるという意味が分からないときの人間の右往左往である。したがって彼がすることは本質的にすべて無意味である。彼の自我は瞑想を通して静かになる必要がある。
- 苦痛という錯覚。もしすべきことがあるなら、その行為に質と量が求められるだろう。努力の量そして技巧の質である。この双方を備えているのは自我ではなく真我である。これが分からない場合、すべての努力と工夫は自我で行われる。したがって結局のところ「私には出来ない」という苦痛という名の優れた教師に直面することになる。苦痛とは間違いを示唆する慈悲である。
我々は肉体を動かすことができる(と考える)。しかし死体は動かない。生きている肉体だけが動き、死体は動かない。物質や形態それ自身では、動くことも話すことも考えることもできない。ここまでは誰もが認めることになる。
ならば肉体で行動している私とは何なのか。何が私を動かし、何がきっかけで動けているのか。肉体の活力自体は動かす者ではない。つまり原理ではない。肉体の活力とは専門的にエーテル体のことである。この活力を通して人間を行為へ駆り立てるのは、アストラル・フォースとメンタル・フォースである。前者は情緒や感情、欲求や気分といった単語を使用するときに我々が感じる力である。後者は想念である。通常はこれらが混ざり合っており、情緒的な想念が肉体を動かしている。
瞑想は、情緒と想念と肉体を静止させるものである。アストラル体とメンタル体と肉体を静止させ、魂に整列させるものである。これら自我意識を構成するものと魂が同一化せず、つまり外へと意識が向かわず、自身である意識自体に意識が向かうとき、つまり単に私にとどまるとき、単に私であるとき、何の抵抗も抑圧もなく”そのまま”であるとき、そのとき知覚され、それ自身として感じられ、よってマインド意識が超越され拡大され、私が肉体でもアストラル体でもメンタル体でもコーザル体でもなく、私が生命自体であるとき、それを世の中では悟りとか真我実現とか呼んでいる。これは本来、科学の分野に属するべき話だが、現代では未知つまり科学が分からないため神秘的に考えられている。したがって知的ではなく、盲目的でアストラル的な瞑想が流行している。ならば、基本的な理屈さえ分かれば、多くのことは簡単になり、また多くの危険は避けられ、学びが正常かつ急速になると我々が言うことに対して、誰が異を唱えうるだろうか。
瞑想の段階
我々は瞑想のために座り、目をつむり、静かであろうとする。初心者は、ここから何かを始める。瞑想ですべきと信じている何かを”おっぱじめる”。つまり、何の力で始められたのか、どの力、どの種類のフォースが自身を動かしたのか、立ち止まってここに気づこうとせずに、ただ同一化して、何かをし始めるのである。
例えば想念が起きる。その想念やイメージ能力に応じて何らかの情緒が呼び起こされる。あるいは、想念をしずめようという想念と同一化する。一事が万事、マインドの内部で迷子になっている。しかし、迷子になっているのは自我である。我々は自我ではない。自我の動きを離れて見る者である。形態の内部から形態の質料に働きかける者である。同一化してはならない。
通常は同一化の誘惑に負けて、自分が迷子になったと感じることを自らに許す。そうすることで、「もう瞑想など分からない」と言って自己憐憫という名のアストラル・エレメンタルに奉仕したり、あるいは真剣さや意志や努力を個人で解釈して必死で集中しようとして頭痛や発狂に見舞われたり、ことごとく自分で何かをしようとしている。瞑想とは、その自分と関係がなくなることである。それによって、ただ真我にとどまることである。したがって次のような段階でものごとがすすむと言ってもいいだろう。
- 最初に同一化があり、私は肉体だと人は言う。肉体が死ぬまでは特定の人物だと信じて自作自演を続ける。
- 離れた観察が訪れる。私は肉体ではないと人は考えはじめる。彼は自己と非自己の識別を開始する。
- 概念で捉えることをやめ、流入し始めるエネルギーの助けを借りて、エネルギーとフォースを識別するようになる。また、高位のエネルギーに対し、低位のフォースはいずれも無力であることを理解するようになる。この認識により、フォースさえ統御できれば何も問題ないことを人は理解する。したがって、出来事や運命を超越する力がすでに備わっていたことがこの段階で教えられる。
- 流入を遡ること、流入に従うことで、人は魂に到達し、真の自己への集中がはじまる。これが観照へと導く。
- 人は高位のエネルギーの伝導体となり、流入したものの流出、つまり神の目的に少しずつ関与できるようになり、自身を囲う形態の霊化を通じて諸体の物質を浄め、高位亜界の物質で構成された高められた波動の意識を通じて、人は生命じたいを認識するようになる。彼は同一化から自由になり、私は形態ではなく命であると言えるようになる。こうして人は神になる。
熟練しつつある瞑想者は、自我の動き、それがどのような動きであれ、まったく興味がない。相反する対をなすもののバランスはとれ、彼という心電図の波形は平坦さにきわまり続けている。だからなにごとも、見て終わりである。気づいて終わりである。わざわざ養分を与えないし、育てもしない。これが魂の特徴である「聖なる無関心」であり、我々が身につけるべきテクニックである。このとき魂である人間は、人間が活動する三界から孤立することで生命の統一に至り、生命という不可分のエネルギーが何を意志し、何を為さんとしているのかを学ぶようになる。これは時間や空間とは関係のない話であるため、マインドで理解することはできない。それは壮大なるものであり、言語や解釈でもてあそぶことが畏れ多いものである。
我々が宿っている諸体は、神秘的に言えば、神の御業をなすための媒体であり道具である。イエスとキリストのような関係である。物質そのものは無だが、そこに命が宿り、命が媒体を動かし、媒体という道具で命が仕事をなすのが自然であるのに対し、我々の場合はマインドが介入し我々を乗っ取る。そのものでは無である物質が低位質料と結びつき、低位エレメンタルを通して、物質が自分であり分離した世界が実在であると魂に錯覚させ、唯一なる生命ではなく、物質と同一化することで個人意識に陥り、神聖なエネルギーを個人の目的のために誤用し続けている。これが不自然であり、悪であり、不調和であり、無知である。したがって生命である我々が関わっているのは、不自然を自然に、悪を善に、不調和を調和に、無知を知恵に、物質を霊に引き上げる仕事である。これが目的であり、「私は何をすべきなのか」という問いへの答えである。
人の子らが物質と質料の間に存在する違いを知ったとき、この時代の教訓は理解されるであろう。他にもまだ教訓は残っているであろうが、それらは乗り越えられる。物質と質料は共に暗黒を作り出す。質料と目的が混ぜ合わされたとき、それは光の道を指し示す。
第六段階のイニシエートの言葉から