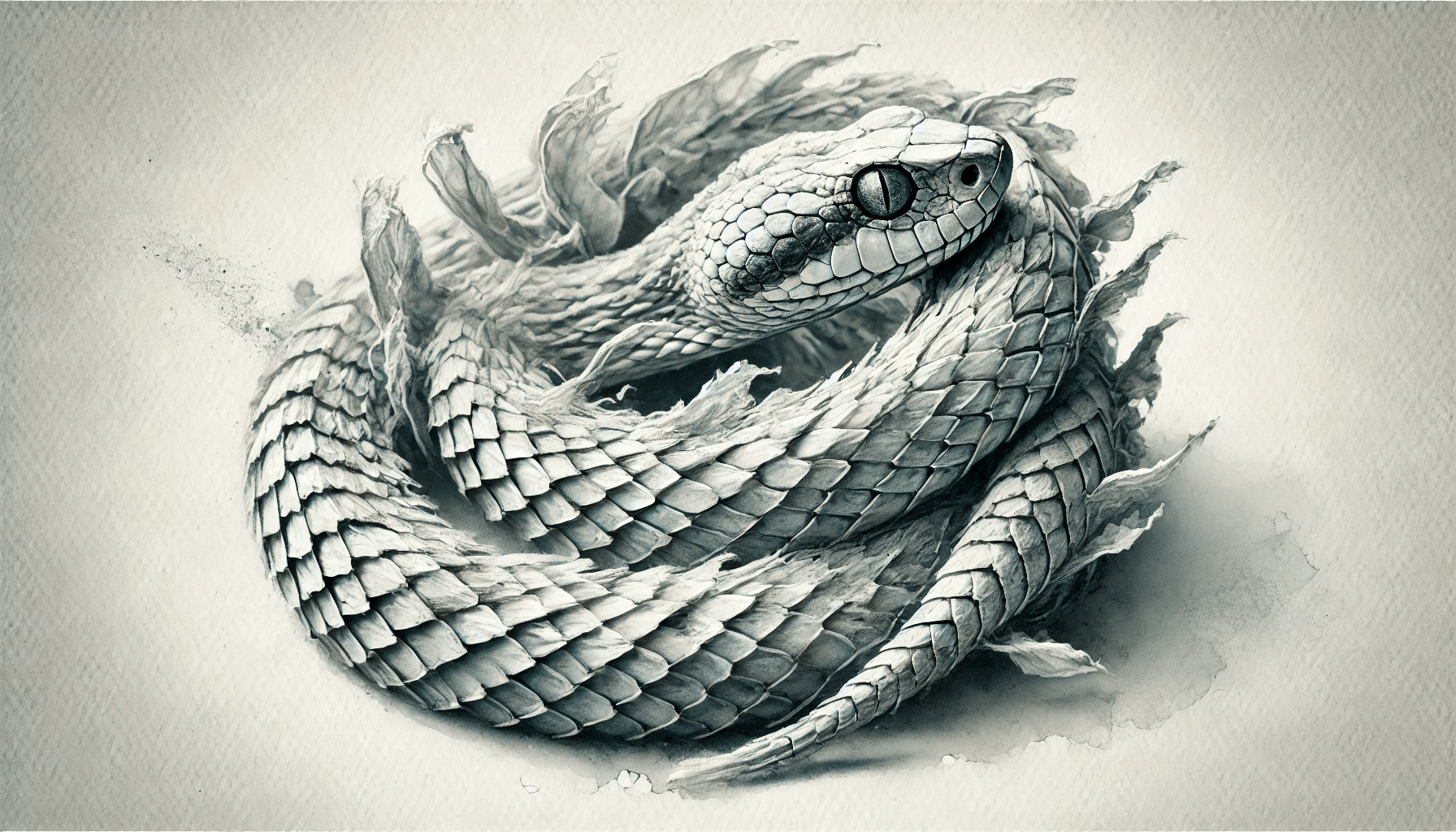- 至る方法はあるのでしょうか。ないのでしょうか。ないのなら、人間は途方に暮れます。
途方に暮れる人と真のあなたは何の関係もないから問題ないのだが、これが分からないという無知が問題を作っている。「至る方法」と言うとき、あなたは内ではなく外へと向かう。つまり、低位我で何かを行っても、それは低位我の世界に属し、よって低位我を拡大するだけであることを、少なくとも理論的には納得しないといけない。それより、「至る方法」が必要なのはなぜなのか。何をあなたは恐れているのか。何から逃れんとしているのか。こういう動機の側面に焦点を戻し、あなた自身を知ろうとすることが求められているのである。こうして、人は外ではなく内へと向かうようになる。いわば、これが「至る方法」である。
- なぜ動機を知ることが「至る方法」になるのでしょうか。
動機では到達できないからである。そして、動機が到達を妨げているからである。例えば人生が苦痛だから真我の世界に逃れたいと人は思っている。無理だろう。彼は苦痛を見ていない。真我という理想や概念を見ている。苦痛から非苦痛へ逃げようとすることは無知である。苦痛からは決して逃れられないことを知り尽くした後に、ならば苦痛を見てみようとする勇気が無知への一撃となる。答えは常に今、この内に、目の前にあることを真に知らねばならない。知るとき、いったい外の教師がなぜ必要だろうか。あるいは外に、理想に、概念に、なぜ魅力を感じる必要があるだろうか。外に求めるもの、必要とされるものは何もない。探求というものは、すべて自己完結できるというのが鉄則であり、それを理解することが道の最初の極意である。
- 人間の行為に全く動機がないことは不可能だと思います。常に何かしら動機があるはずです。その動機を無限に見て、終わりなどあるのでしょうか。
そのとおりで、「動機を見る」こと自体にも動機がある。ここに気づくとき、一瞬、思考は止まるだろう。つまりマインドの世界のいかなる戯れも、行為も、その領域を巡回しているだけで、左から右、右から左へは移行できても、下から上へは行けないことを知るだろう。探求もしくは瞑想とは、それを行う者の打破である。言い換えると、低位我を知ることによる低位我の静止、これが高位我の認識へと導くのである。そして高位我へ至るような者は、「至る方法」などに常に興味がない。同時に、「至る」必要性にも関心がない。それらの病的傾向はただ見られ、気づかれ、その都度、同一化を遮断されるだけである。この見るということ、気づくということには、いかなる動機もない。なぜなら、見ているのはもはや低位我ではないからである。
- 低位我は常に動機を持ち、高位我のみが動機から自由である、という可能性は理解できたとして、低位我である私は低位我ゆえに、常に動機で行為するだけです。高位我ではないので、動機に動かされることしかできません。私には何もできません。しかし私は常に行為します。動機に行為させられます。この悪循環の解決法が見えてこないのです。
そのような場合も、見えてこなくていいと感じるべきである。またしても、あなたは低位我の物語に入った。マインドの詐欺的な想念や情緒に揺さぶられて、個人の物語で低位我を拡大しようとし始めた。こんなことに騙されていてどうするのか。あなたを揺さぶるいかなる情緒も、想念も、騙そうとするための道具でしかない。つまり自作自演のためのものである。真我は、真に知性であるゆえ、そのような自作自演に全く無関心である。逆に、あなたがあえて関係しに行くかぎり、どうやっても真我は認識できない。霊的な態度の秘訣は不動である。しかし不動とは魂のことである。融合した者だけが不動を授けられる。低位我は常に動揺である。だから動揺の中身が知られ克服されるまで、高位我は認識できないことを知り、おのれを知ることでおのれを統御するすべを突き止めねばならない。
- しかし我々は動揺に対処できません。
対処しようとしてはならない。関わらないように言っているのである。それは動揺から目を背けることではなく、動揺自体を見ることである。やや逆説的だが、ここでは見ることが関わらないことなのである。見るとき、そこには、対象をどうにかしようという意志は全くない。だから単に目だと言うこともできるだろう。前回の記事的に言い直すと、魂の目で、第三の目を通し、エネルギーを対象のフォースに差し向けるだけである。すると、在ったものは無くなるのである。おのれを見ること、動機をただ見ること、これは初歩的な段階だが、あるとき、あなたは概念の世界を打ち破るだろう。つまり、命名しないようになる。例えば最近の記事で言えば、寒いとき、その感覚に「寒気」などの用語で確定させないだろう。なぜなら、命名とは認知作業だからである。命名し認めるとき、その存在に力を与えるのである。よって疑うようにすすめた。概念や命名による認識を打破し、そのような想念形態の側面ではなく、それらを単に活動しているフォースとして見るならば、何事も命名なくして、何であれフォースをエネルギーによって変性しようという最初のオカルト的な発明に到達するだろう。驚くことに、これで多くのそれまで存在してきたものが無効化されるのである。
- 多少わかってきたような気がします。私は動揺しやすく、また動揺自体に力を与えてきました。それは確かに自身で認め、強大化し、存在としてあらしめる自作自演のように思われます。この過程をどうにかしようという考え自体が対象を強めてきました。つまり、私はこれまで霊的な方向とは逆のことをやってきたように思います。「至る方法」という強迫観念もまた自作自演でした。自作自演の意味がわかってきたと思います。そして自作自演の循環から離れていること、これが自我からの脱却の鍵であるということを理解しつつあります。
するとあなたは気づき始めるだろう。恐れるものがないことを。言い換えると、何事も統御できるということを。それはあなたという諸体の透明度の問題であり、透明であるとは、低位質料、低位のフォースが霊つまり一なるエネルギーによって純化されたことであると。したがってなぜ我々が想念や概念ではなく、常にエネルギーとして質料やフォースと関わっているのかを理解するだろう。霊として魂を通し物質と関わっているのかを理解するだろう。我々は命名することで固定せず、具体化する前のものを扱っている。凝結する前のものを扱っている。結果ではなく原因を扱っている。この意味が分かるであろうか。我々はやがて、何のために物質に宿っているのかを理解するだろう。我々が死人を見るとき、あるいは生きていた者が死ぬ瞬間を捉えるとき、何かがその物質から去ったことを理解する。霊つまり生命として、我々はいま物質内の環境に意識を置いている。そして物質の質料に動かされている。逆に、霊が物質を統御し始めるとき、神や、神の目的が理解されるようになり、知的に、意識的に、神の目的に参画するようになる。秘教徒が外から内へ至るというのはこの意味である。この至る過程は決して個人的な動機からではなく、この過程全体を統御している愛と呼ばれる神の生命エネルギーによってである。
至るという病