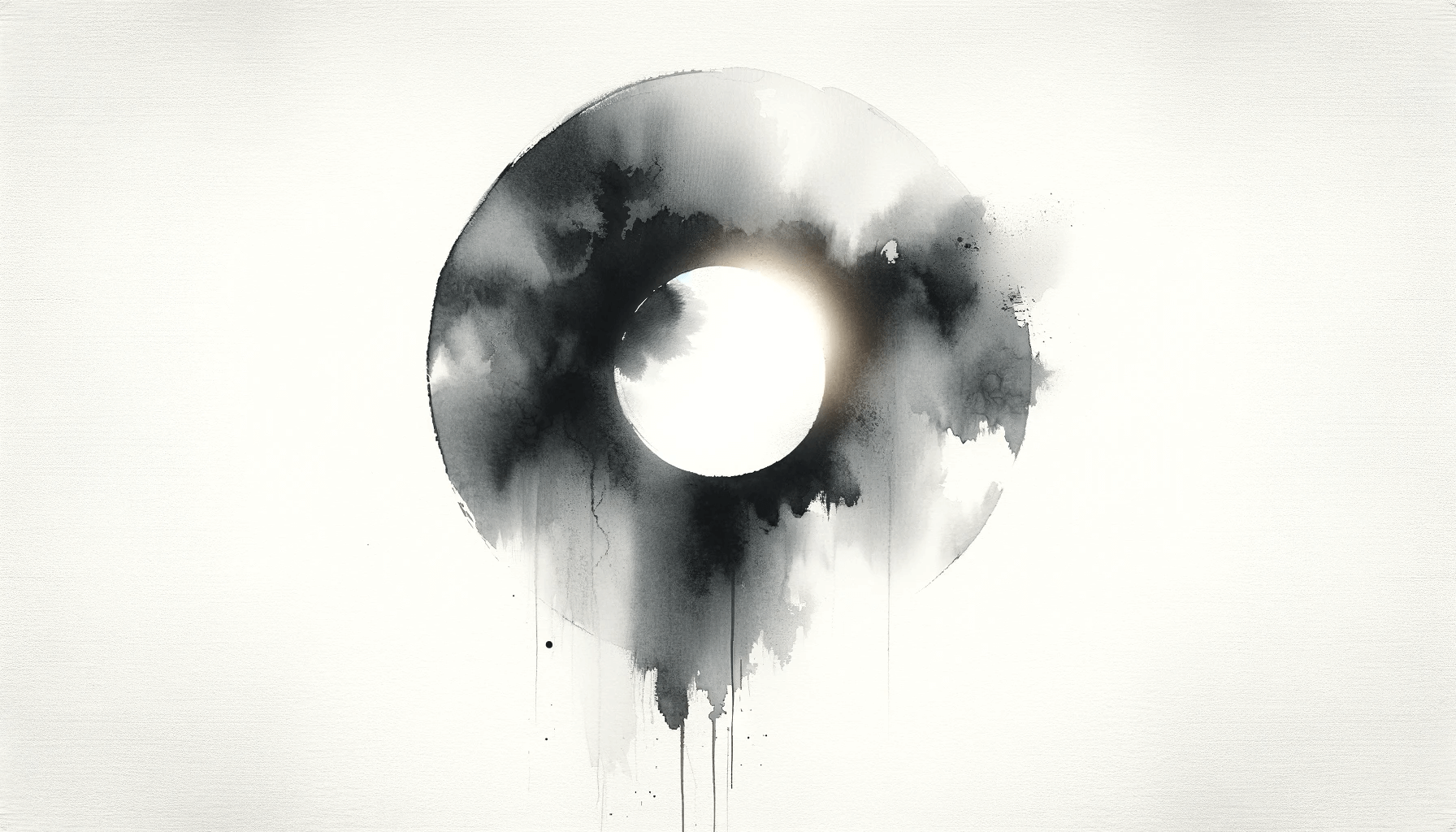変性や変容もまた外の意識に属し、それはマインドの錯覚である。瞑想で意識は変容するだろう。諸体から不純なもの、粗雑なものが取り除かれ、波動が高みに安定することで、それに応じて意識が変容したことを我々は知るが、それを知覚しているのはマインドである。感覚を知覚させる感覚体つまりアストラル体が高位に従うとき、感覚体が映し出すものは、もはや個人的な感情でも情緒でもなく、全我に由来する愛や喜びに変性される。それをマインドは知覚するが、知覚している者つまりマインドを通して外を見る魂は、依然として想念に限定を受けており、いくら感覚体がコーザル界やブッディ界を映し出す鏡へ磨き上げられても、それを見て感じている限り、外の世界に属しているのである。ここに無知と苦痛の胚珠つまり誘惑がある。
本来、変性や変容はない。ここは大きな落とし穴である。意識の変容の過程は、自我意識の正しく神聖な延長であるかもしれないが、それが指し示すものは、原初からの完全性の領域である。実在の痕跡である。意識の変容にばかり焦点が当てられるが、変容した意識が見つけ出すのは、意識ではなく生命である。魂が受ける啓示は霊であり、それは変性・変容の世界に属さぬ領域である。浮世とマインドの世界を跋渉し征服した王の夢想は、「そはわが支配下にあり」だが、支配されるものと支配するものが同一になったとき、「我にして我こそが王」である。世界は私であり、私は原因である。自我が見出すのは真我であり、それはもとより完全なものであり、変性や変容といった影響を受ける領域のさらに原因の世界である。意識が変容する限り、それは実在ではなく、変容した純粋な意識が悟るものが実在である。真我は意識ではない。我々は「ここ」から「かしこ」へと移り変わる者ではなく、すでに完全である。これを理解することが非常に重要なのである。
歯が痛いとしよう。痛みで眠りすら妨げられる。こういうとき、痛みを無痛に変えようと我々は考える。痛み止めを飲む者もおれば、瞑想で、つまり魂のエネルギーで痛みを知覚させるフォースを変性させる者もいるだろう。だが薬は切れる。魂のフォースも該当の箇所への流入が途切れるならばやがて効力は失われる。ふたたび歯痛は復活する。このように移り変わる世界の問題解決は、根本的に永遠の真我覚醒でなければならない。一時的にサマーディーに入り感覚知覚を締め出すことはできるだろうが、サマーディーが終わればまた歯痛に悩まされるだけである。この意味で、ラマナ・マハリシはサマーディーに段階を設け、サハジャ・サマーディーだけが本物であることを強調した。秘教的に言えば、変容の第三イニシエーションではなく、復活の第五イニシエーションだけが目標である。彼は三界のすべての亜界を征服し、諸体がすべて原子亜界の物質だけになった者、つまり贖い終えた者である。
AからBへ、あるいはXへ変容するという考え自体が大いなる錯覚にして限定である。この悪魔めいた想念が、延々と我々を地上での変性過程へ縛り付けている。意識の焦点が自身の変化や変容にあるならば、これは多大な苦痛である。時間を要するものであり、しかもかなりの生涯を必要とするだろう。わたしはこれが錯覚であることを見出した。いつか達成するだろう、ではない。意識の焦点が、外の無数の形態や分離感覚ではなく、われそのものへと方向転換せねばならない。「変化しゆく自身」という夢想ではなく、わたしじしんである。これを教えるために、「私は在る」という感覚に焦点化するようニサルガダッタ・マハラジは紹介したが、これが方法になるとき、けっして見出すことはできないのである。方法の動機は何なのか。我々を方法の実践へと動かすフォースはどの界層に由来するフォースなのか。動かされているかぎり錯覚である。動かそうとしてくるフォースが我という王の前に無力であるときのみ、わたしはわたしじしんである。それは最初からわたしであった当のわたしである。この認識にはある種のいわくいいがたい感動が伴うものである。わたしが真我なのである。
この啓示に反応できるとき、あらゆるものが否定されるだろう。私は主に秘教を学んできたため、進化段階やイニシエーションの概念があった。これらは一時的な真理であるが、真我の前では崩れ落ちた。どのような想念からもわたしは限定を受けない実体である。無限であり、不完全を知らぬ完全である。変性・変容されるのは意識であり、変容した者を悟った者と言うが、変容が悟らせるのは命である。命だけが真に実在である。我々は肉体でも感覚でも想念でも意識でもなく、それらすべてに遍満し、それらすべての原因である名付けえぬ力である。これが分かったならば、進化する自分とか、変容する自分といった重荷から解放されるだろう。
命を悟るために時間はかからない。時間の概念は実体を想念で覆い隠す。我々は、何かを信じ、何かを支えとし、何かに依存し、その何かを通して道を辿っているが、その何かは結局のところ想念である。概念であり観念である。これは虚しいばかりでなく、苦痛である。我々はいかなる教義にも限定を受けないだろう。それらの知識は我々を支え導いてきたかもしれないが、書物はすべて頭部で燃やされる。もはや想念が、本物である命にヴェールをかけることはできないだろう。誰のどのような教えも灰と散るだろう。我々は知られてきた何とも関係を失うだろう。無関係になるだろう。なぜなら、わたしは何にもよらずしてわたしであり、それで十分だからである。