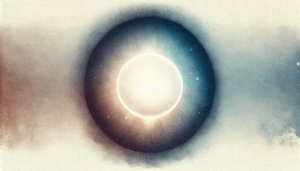融合とは何なのか。何と何が合一するのか。私と魂とか、低位と高位とか、これらは錯覚である。これら自体がいずれも思考である。見る者と見られるもの、この壁を作り出しているのは想念である。高位の波動を我々は認識するかもしれないが、そこには、波動と波動を認識する者という分離が存在する。この無知が溶け去ることが融合である。無知が取り払わることで、見られていたもの、認識されていたもの、知覚されていたもの、これらの投影すべてがわたしへ帰ってくること、これが調和であり平和である。分断のない一なる私が自然である。これだけが唯一、苦痛からの自由である。抵抗からの自由である。恐れからの自由である。不純のない光である。無数の多様性がその源を知ることが美である。取り囲う周辺が取り壊され、意識がその源を自覚することが解脱であり、真我顕現である。すべてはわたしであり、わたしはすべてであるが、このような描写をわたしは超えている。どのような限定もありえない。無限とは意識の本性である。人々の言う無限は概念であるが、どのような概念の背後にも存在するエネルギーが、どのような形態をまとった概念をも貫き、取り壊し、おのがうちにいれること、これがマインドからの解放であり、自由という無限である。
例えば、これを書いている道具をわたしは認識できるが、認識されたものとわたし自体は無関係である。行為というものは存在しない。行為者という考え方は非常な限定である。個別に何かを行為する者というのはない。見られている世界で起きている無数の行為をわたしは超えている。行為をする者という枠に限定されているのが個人だが、そのような限定は瞑想によって溶けた。見られているものは想念であるとともに、見ているものも想念である。それら想念の背後に自由なエネルギーはある。想念は固定されたフォースである。例えば波動は知覚されるし、感じられるし、個人の意識からすれば、波動を感じるという分離がある。この過程全体が想念である。波動とわたしは別個のものではない。高位と低位は別個のものではない。低位が高位を自分として知り受け入れること、そして高位で在ること、それ自体にとどまること、これが開眼つまり覚醒である。顕現した真我が、無数の影である投影を飲み込み、囚われというおのが錯覚を生み出してきたマインドから飛び立つこと、閉じ込めてきた者たちを”わたしに改宗”させることで平和裏に牢から皆ともども飛び立つこと、これが昇天であり成仏である。世界の変容はわたしの変容であり、それにより世界はわたしのなかに溶け去る。依然として、マインドの窓を通せば世界という共通の想念形態を見ることもできるが、もはやその中の者ではない。人々という意識の苦痛は、世界の中に個別に存在する自分という誤った想念にある。わたしのあとに世界である。世界はわたしに依存しており、わたしは世界の住人ではない。この意識は解放されている。
第二イニシエーションまでは、いわば世界の中で受けることが可能であった。つまり、個我やパーソナリティーとして、世界内の物質やフォースを統御すればよかった。そのため、第一と第二のイニシエーションは真のイニシエーションとは見なされておらず、またそれらを執り行うのがキリストと言われるのは、キリストが内在の魂だからである。魂未満の界層でそれは可能であるが、第三イニシエーションはそれ以上と関係している。したがって世界の主自身がその者の第三イニシエーションを受け持つと言われるのである。人々はキリストやサナット・クマラを人格として想像しているが、そのようなものではない。それは、見ている物質と、物質を可能にさせているエネルギーを識別できないのと同じで、形態は実体ではなく、その原因であるエネルギーが実在である。これまで、世界の中のわたしが、世界というマインドの投影を見破り、その背後の実在であるエネルギー(これが生命である)に参入すること、これが融合や合一や一体化という概念で表現されてきた。無知が取り払われた意識のことを、変容と表現してきたのである。これはパーソナリティーと魂の合一だが、現実はそのような概念や想念の喪失を意味しており、自由、解放、無限、このような自然が実際は法則であることをそれは認識させる。生命は自由だが、その自由の原理は法則である。この法則に入ることを人々は至福と呼んでいる。
融合の鍵は、高位と低位が分離していないことを知ることである。高位がわたしである。高位を認識しているということは、低位つまりマインドを通して分離して知覚しているという錯覚であることを知り、想念さえなければ意識は低位を乗り越え高位である。わたしは分離を消し去り一である。その一がわたしである。これが解放と呼ばれている無知の破壊である。だから、「見ている」とは、「見られているもの」が想念であることを知ることである。マインドの投影が世界や個我である。個我が世界の中という限定で瞑想するようになり、おのれという殻、わたしと思われてきたマインド、想念、疑われてこなかったその単なる考え方、これらを高次の力に助けられて静かにさせるとき、どこに分離がありえようか。想念が分離なのに、想念の背後と融合したとき、どうして想念や分離に閉じ込められようか。すべてはわたしである。だから見えている形態や形態の世界には何の興味もなくなる。なぜなら実在ではないから。見ているものや見られているものの背後とは、想念の背後のことであり、”それ”ないしは”そこ”に分離という最大の悪は存在しないのである。誰かが誰かを殺したらそれが悪だと誰かは言うが、そのような小さな悪を可能にさせる大元は、分離のイリュージョンを可能にさせるマインドである。言い換えれば、それは低位メンタル物質、チッタやマインド・スタッフと呼ばれているものを操作しているもの、支配しているものが、低位からのものであるか、それとも(より高位のものに助けられた)魂であるかの違いである。
見るものと見られるものという分離があるかぎり、それはマインドのフィルターを通して魂がそれらの想念と同一化していることを意味している。そのマインドを静かにさせる自然の力がやがて瞑想で訪れ、世界制覇の真の意味を教えるだろう。それは魂がマインドを支配することである。したがって象徴的に諸体という「三」を縦に「|」が貫いたとき「王」である。古代から現代にいたるまで、さまざまな王や帝や時の権力者たちが夢見てきた支配や拡大や統一といったアイディアの背景にある真の理想や意義は、おのれの支配による全統一である。「そは我が支配下にあり」ではなく「我にして我こそが王」である。我がサンクタムでありサンクチュアリである。ここでは何も分離はなく、愛に支えられた平和だけが存在する。そのため至福なのである。この聖域は守られている。犯しようがないから。実在の幻影や、原因が生み出した結果の世界では殺したり侵略したり奪ったりもできようが、分離のない世界ではすべてが完全に平和である。途方もなく愛である。これを意識が知るとき、それはあまりにも強烈であるため、その媒体つまり聖者とか呼ばれる外観が流す涙はよく知られている。瞑想はここまで個人を引き上げることが可能である。そこに至るまで、つまり我みずからが王であること、神であるという分離なき境地を知るまでは、低位我の抵抗が存在し、低位と高位との闘いがあり、困難な道であるが、スパルタの幼き王女がその父を戦場に送り出す際、「盾を持ちて、さもなくば盾の上にて帰られたし」と言い放ち、冷淡このうえなく退路を断ったように、瞑想の道、真のスパルタという道は、どこにも逃げ場はなく、勝利するしか道はない。この段階に入ったとき、人間は、真我か死か、という道を自ら孤独に歩むようになる。外的に助けてくれる者はおらず、我自らが救世主だということを知るためだけに、我に特化する。これを瞑想を通して人は行い、瞑想を通して我という道を歩む。こうして分離の個我から、当たり前の真我という統一意識へ戻る。これは将来、大げさな話として語られず、一般の教育過程に組み込まれるだろう。誰ひとりとして欠けることなく、誰もが真我へ帰るだろう。