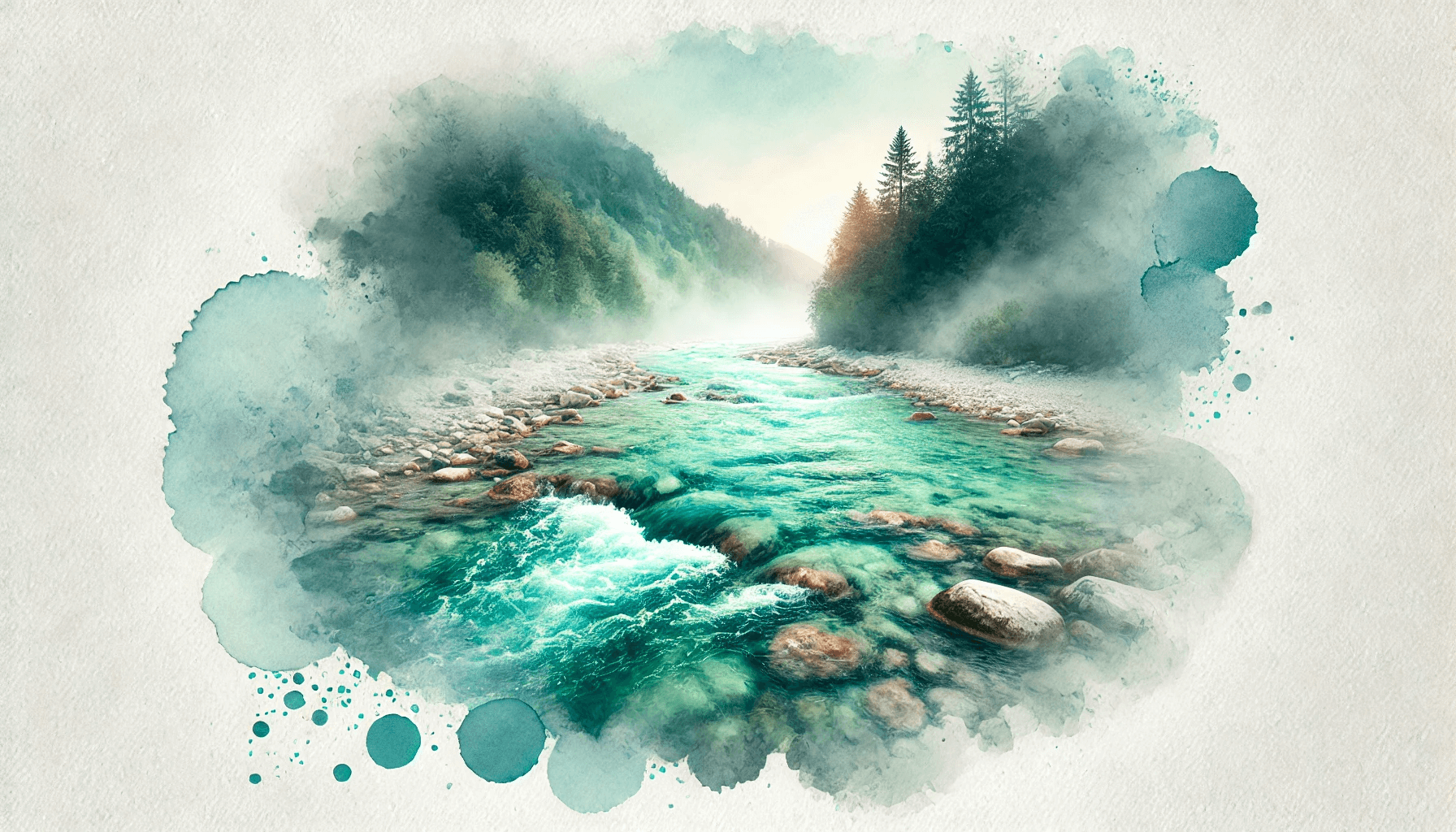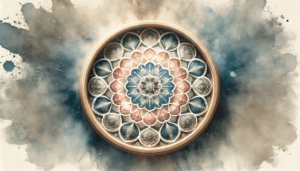「川のない生活はお辛くありませんか」と女性は言った。歳は四十ばかり。短い黒髪に黒縁の眼鏡。大学で福祉を教えているという。新たな棲家に落ち着いた我々が、初めて彼女と相見えたとき、交わされたのは「川」の話であった。
この地は四方を山に囲まれ、その緑は目に染み入るほどに美しい。されど、水の流れは希薄であり、身近な川は枯れ果てている。ゆるやかな流れの美しさを求めるならば、車を駆るよりほかにない。「よい川をご存じだろうか」。彼女はひとつの渓谷の名を挙げた。正確な発音には覚束なさを感じるものの、そこに流れる「青い川」への道を教えてくれた。「折を見て参りましょう」と応じながらも、我々はその名を、しばし忘却の裡に置いた。
時が流れ、ある日、旅路の折に渓谷の麓を過ぎゆくとき、かの会話が突如として脳裏をかすめた。「あのときの道とは、すなわちこの道ではあるまいか」。そう思い至るや否や、我々は車の進路を山道へと転じた。道はやがて複雑に絡み合い、進むべき方角に迷いを覚えた。ふと目をやると、一人の男が歩いている。彼に尋ねてみるべきだろうか。「この道で間違いはございません。ただし、大きな交差点の手前にて、左へと折れねばなりません」と、彼は静かに告げた。礼を述べ、車を進めながら、我々は彼の笑顔の無垢なることに心を奪われた。それは疑念を知らぬ、まるで幼子のような、あるいは信頼に満ちた大地そのもののような表情であった。
この地に住み始めて最初に気づいたのは、人々の自然な善意であり、まるで囲いのない庭に咲き誇る花々のごとき素朴さであった。道行く者は見知らぬ相手にも微笑みかけ、「こんにちは」と親しげに言葉を交わす。同じ住まいに暮らす子供は、家へと戻るたび、無邪気な挨拶に満面の笑みを浮かべる。家々には丹精込められた庭があり、四季折々の花が彩を添える。ある日、三十ばかりの中学教師と知己を得た。彼女は言う。「学校に行くのが好きなのです」。学校を好む教師とは珍しい。「子どもたちはみな、心根の良い子ばかりです。不良ですか? 一人もおりませんよ」。彼女は笑いながら答えた。我々はふと、この町に移り住んで以来、荒んだ人影をひとつも目にしていないことに思い至った。人口は決して少なくない。それでも、夜の歓楽に溺れる場はなく、警察官は穏やかに日々を過ごしている。市役所の職員もまた、友のごとく、親しみをもって応対する。
このような話を交わしながら、我々は「青い川」と思われる渓流のほとりにたどり着いた。そこは人の気配のない静謐な観光地であった。道には丁寧な案内が施され、我々は川のせせらぎを横に聴きながら、整えられた遊歩道を歩いた。
幼き頃の記憶がふと甦る。夏の日の遊びといえば、川がすべてであった。流れに手を浸し、陽の光を浴びながら、水と戯れる時間こそ、心を解き放つものだった。眼前の流れは穏やかで、岩間に響く水音は、あたかも遠い過去からの囁きのように静かであった。
後日、我々はこの旅の話を、あの女性教授に語った。彼女は微笑んだが、次第に表情を曇らせ、「申し上げにくいのですが……」と口を開いた。「そこではございません」。驚きながらも、我々は即座に理解した。我々は途中で左へ折れ、整えられた道を進んだ。だが、本当に「青い川」へ至るには、手前の小道を右に下らねばならなかったのだ。「それゆえ、地元の者しか知らないのです」と、彼女は言った。
人は目的を抱くと、それに向けて道を敷く。されど、しばしばその道は自己の幻影に過ぎず、真に求めるべき地へは至らぬ。目的とは、しばしば人の想念にすぎない。我々は「青い川」を探し求めたが、たどり着いた流れは青くなかった。途中で確かめることもなく、教えられた方向へただ進んだ。そして、それを目指すべき地と信じ込んでいたのだ。
瞑想においても、同じ過ちが繰り返される。あるべき境地を求め、それが書物や教えに示された道であれば、正しいと考える。しかし、それは伝えられる過程で歪められた想念にほかならない。目指すべき地とは、本当にそこなのか。
いかなる知識も、いかなる見聞も、それが現在ならざる限り、欲望と恐怖の影のなかにある。それは信仰を盲信に変え、やがて狂信へと至らしめる。目的地とは己の投影にすぎず、それが真理へ導くことは決してない。AからBへと進む道は誤謬である。我々はすでにAであり、すでに現在にあり、そしてすでに目的地そのものである。されど、もしそれを見出せぬならば、それは無知がその光を覆い隠しているがゆえである。その無知とは、情緒と想念の産物にほかならない。