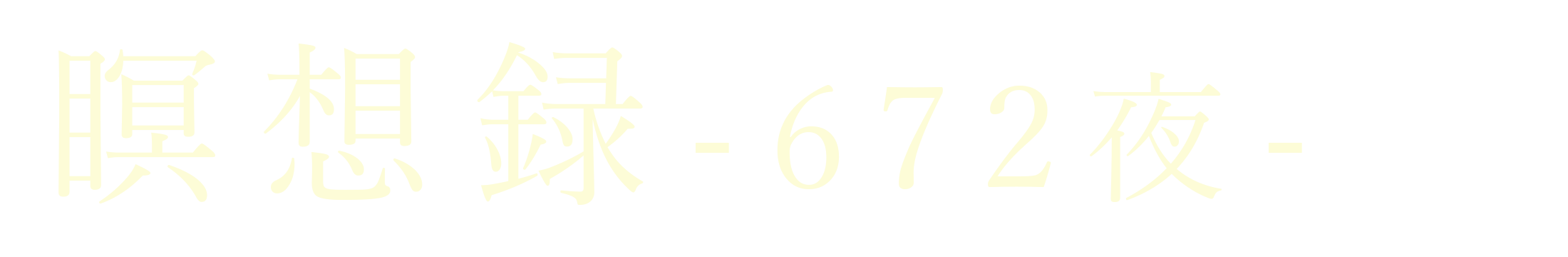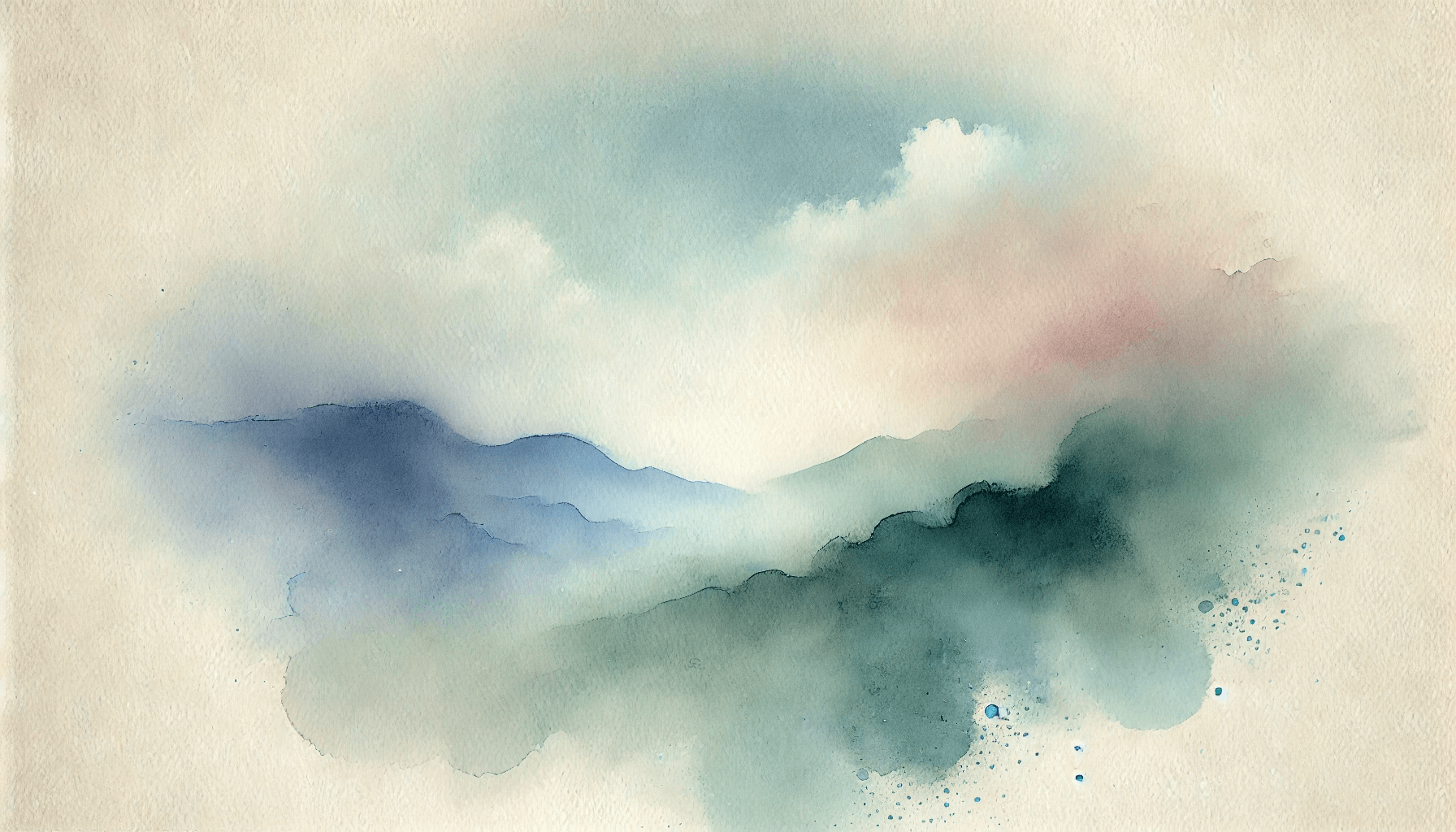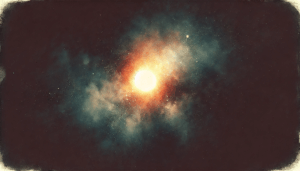学者との対話
「理解とは分析と結論の産物ではないでしょうか」と或る学者は言った。彼のような知性は、思考を通じて理解しようとする習慣が染みついている。しかし霊的な真理は、思考を超えた領域にあり、思考を通じてアクセスできるものではないのである。
「しかし、歴史上の霊的指導者たちも行為や実践を重視していました」と彼は続けた。「もし観察だけで十分なら、なぜ彼らは教えを残し、何かを『する』ことを説いたのでしょうか。思うに、霊的な成長には、『内的な気づき』と『外的な実践』の両方が必要なのです。というのも、何かを理解しても、それを外に表現しなければ意味がないからです。したがって、『内的な気づき』を『外的な実践』に転換することこそが、霊的な変容につながるのではないでしょうか。つまりは、観察だけでは不十分であり、観察の先には何らかの行為や実践が必要なはずなのです」。
観察の先にあるもの
この学者は、数人の「覚者」の名前を挙げた。そして彼らが、カルマ・ヨーガ、バクティ・ヨーガ、ラージャ・ヨーガを認め、内的な理解を外的に表現することこそが、霊的な変容をもたらすものと主張した。日本人的に言えば、奉仕活動に励み、仏像や神などを拝み、お教を唱え、祈りを捧げ、善い行いをしようと努力することを指すだろう。隣の芝生は青いため、ヨーガと言えば聞こえはいいが、このように言い換えると拒否反応を示す人もいるだろう。しかし、同じことである。
学者は、「内的な観察の先の行為や実践が鍵」であると言う。そのうち、クリシュナムルティの話になり、「あるがままの観察だけでは足りないはずであり、観察の先に、何らかの実践があるはずだ」と言うのである。私は「実践」を否定はしないが、どのような行為をしようと、その背後に実在は存在しているのではないだろうか。彼が善行に励もうが、悪行に身を染めようが、魂はそれらに関係なく背後に存在しているのではなかろうか。
要点
学者は自己を非自己と同一化し、「学者である自分」として生きている。その非自己が何かをすることで、本物の自己に到達すると思い込んでいる。よく考えれば分かることだが、原因と結果が逆さまではないだろうか。非自己の前に真の自己は存在していたはずである。言い換えると、真我は、自我の行為に依存していないのである。
思考を超えた領域の話
もしこれが分かるならば、即座に到達する。それぐらい重要な話をしている。私が最初に「思考を超えた領域」に入ったときのことを再び話そう。当時の私は苦しんでいた。その後、冷静に考えると、自分はあらゆるものに恵まれていることに気がついた。つまり外的な話である。しかしなぜ内側は不幸なのだろうかと思った。人々が欲するものを自分は持ち合わせているが、なぜ自殺しようとしているのか。つまり最終的に、「何に苦しんでいるのか分からなくなった」のである。この疑問が、何の苦しみなのか、苦しみはどこから来ているのか、何がこれほど私を苦しませているのか、といった本質的な問いへ導き、苦痛そのものを「あるがままに観察」させたのである。
次の瞬間、私はその苦しんでいる者から切り離された。真我は、自我の埒外にただ存在しており、それは途方もなく美しく、素晴らしく、喜ばしく、至福であるものであった。私は、自我というものがすべて心の自作自演で生じていたことを理解した。真我は、個人の意識とは全く別次元に存在しているが、それはまったく私自身として最も身近に存在していたのである。次元とは、別の場所という意味ではないのである。意識レベルのことである。私が苦痛を「あるがままに観察」させられたとき、それは勝手に起こったのである。こうして、その保護された領域に入ることがやがて自在にできるようになった、というだけのことである。そして自我は、その領域で本物を学び、再び自我に戻される理由を学び、そこへ頻繁に出入りするようになり、そこに在ることが習慣のようになり、徐々に自我の性質から解放されていったのである。よって、真の観察であれば、それは直接的に「思考を超えた領域」へ導くことは事実である。
しかし、このような観察を個人がしようと思ってできるものではないのである。なぜなら、人は到達するためという邪まな動機でしか観察できないからであり、「純粋な観察」が起こるのは、瞑想で深い意識へ導かれたときか、私のように極端な苦痛で精神が完全にそれと対峙せざるをえなくなったときか、いずれにしても、意図して引き起こすことのできるものではないのである。
真の観察は即時に心を静止させる
真の観察とは、観察の対象に純粋に興味をもつことで生じる。観察の動機は、観察される対象への疑問であり、もしくは興味である。するとどういうことが起きるだろうか。思考者(私)と思考(苦痛という解釈すなわちカーマ・マナス)というものが見つめ合ったとき、思考自体が消えるのである。われわれは分割して物事を考えているが、それらが互いを見合ったとき、その正体に迫ったとき、「見る者と見られるもの」という分割がないことが知られるのである。つまり何も分割のない純粋な一つの意識にすべてが集約されることが起きる。こうして、自我は消え去り、真我が顕現するのである。
探求者の観察
平均的な観察は、学者が冒頭で述べた「理解とは分析と結論の産物ではないでしょうか」という言葉に表されるものである。それは理解を求めるものである。観察から別の答えを導き出そうとする試みである。観察される対象そのものが答えであることを知らないからそういうことが起きる。観察している私と、観察される対象というものは、同一である。真に見るとき、観察するとき、分析などの思考は存在できないのである。
我々は世界など何かを見ているが、それは全くの幻である。私の上に、いわば普遍マインドを通したものが投影され、その映っているものが、あたかも我々は存在しているかのように思っているだけである。その源とは私なのである。だから、「原初の私」という記事はそのことについて書いた。触ることができるから存在していると我々は考えるが、感覚によって存在を証明しようとするかぎり、「感覚されたもの」の背後の実在つまり私(真我)とは見当違いなものを思考しているのであり、このようなすべて見えるもの、映し出されているものの前に、私が原初であり、私が本質なのである。これは、別に思考しながらも完全に理解し、また超越した意識であることが可能なものである。
超越
超越とは、そのとき、私そのものであったことが知られるだろう。だから、非超越という想念があっただけなのである。世界の後の私とか、親によって生まれた私とか、そういう見た目上の話や体験といった想念や思い込みに生きているということが檻だっただけである。私はすでに超えていたもの、と言うより、私しかないのである。世界などは、その後におきた想念の結果である。こういうことをマーヤーとインド人たちは言ったが、何かが見えることは、見えているものにあえて限定され閉じ込められることを必要としていないのである。見えていても関係なく、見えるものを可能にさせている「それ」はここに存在している。だから瞑想する者は、かえって目を閉じるがゆえに、その閉じていることに安心して、想念を野放しにしていることが多いのだが、目を開けた瞑想というものをここで提唱したい。見えているものすら、
書きながらここで「書くことのできない意識」に入ったため、そこから数時間が経った。こうして記事が途中で頓挫し、記事を上げることなく破棄されるものはこれまでいくつもあったが、今回のものは途中から重要な話を含んでいるため、あえてこのまま上げることにする。