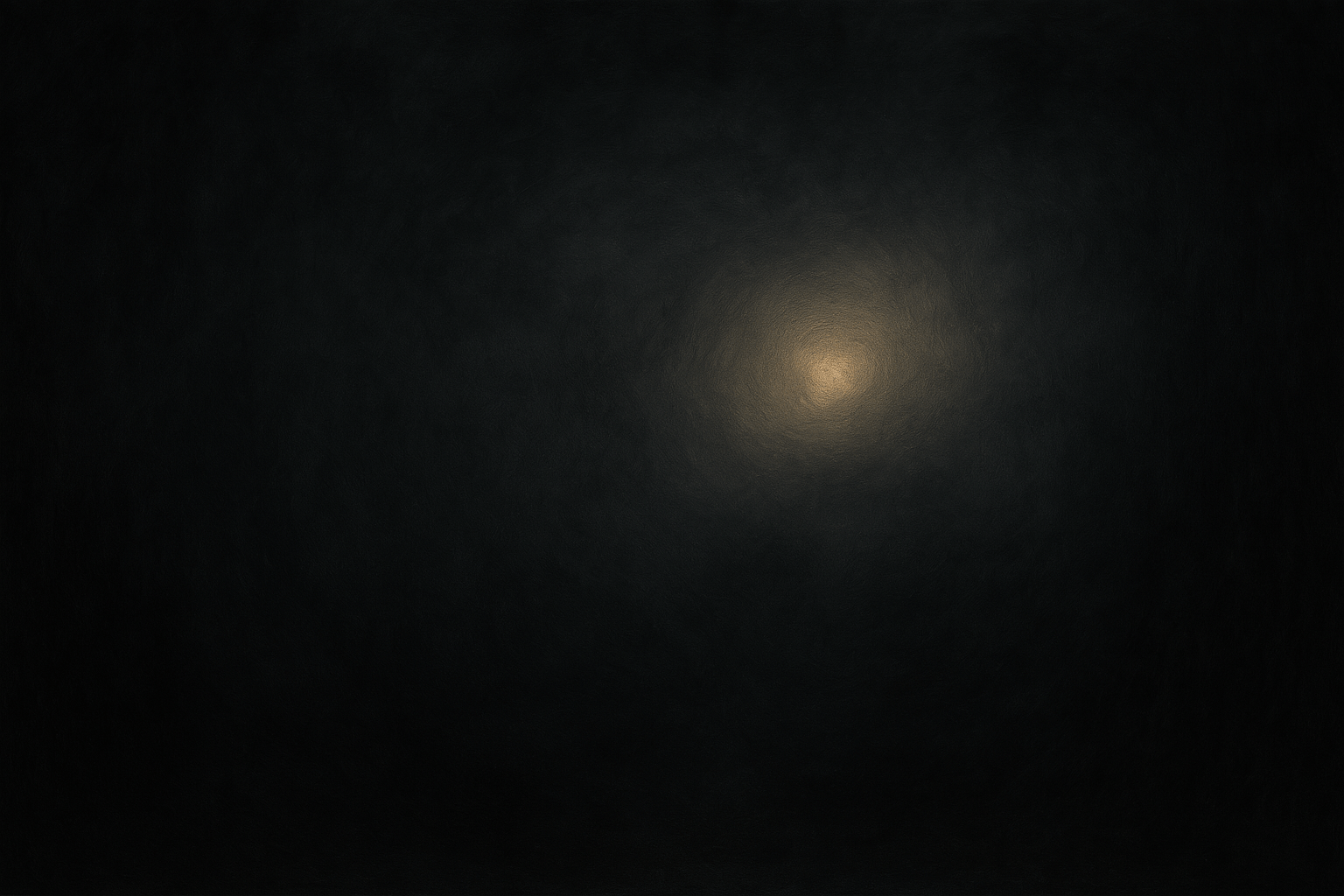個人は、絶望的である。
だがそれでよい。
個人は、その性質の絶望性をいつかは知らねばならない。
ところが現実には、個人は希望に生きている。
未来を信じ、向上を信じ、探求を信じている。
そして自由意志を信じている。
そのような希望は、個人の背後にある実在を知らぬままに抱かれる個人の私物にして無知の産物であり、
実在がまだ臨んでいないために、個人は個人で在り、且つ個人で未来を描くことしかできない結果でしかない。
その状態で絶望が訪れれば、個人は壊れる。
自殺とは、背後の光が訪れていない個人における、
一切の居場所の無さという錯覚の終点である。
だがもし、個人が何もできないということを理解できるほどに成熟しているならば、
その絶望は、有用でしかない。
なぜなら、それは個の静止を招き、静止は魂という秘められた意識領域を個に教えるからだ。
こうして、魂を介して意志が働き始めるとき、
その破壊作用は愛と慈悲の波動の中で行われる。
魂という「救いの地」が存在するかぎり、
個は破壊の中にあっても至福である。
だが、魂をまだ知らず、接触を求めているだけの者、
すなわち見習いの弟子の段階にある者にとっては、
この破壊が起こることを可能にさせるための浄化期間を、
極度の孤独と苦悩の中で通過されねばならない。
この時期は、きわめてぎりぎりのものになる。
ジュワル・クール覚者は語っている。
敷居の住者に圧倒されて自殺する弟子は少なくない、と。
個からの脱却が始まる直前、
個の無価値性が深く知られなければならないのだが、
それが分からず、個としてあくまで実在に挑もうとするとき、
彼は自身が無能であることに絶望し、自殺してしまうのである。
もし個が個の無価値と無能を悟り、受け入れ、諦念の真の価値を知るならば、
意志という愛の破壊が個人に訪れる。
真理自体が、個人の殺戮のために現前するようになる。
それが起きるまでは、個人はまだ楽観している。
個人的な探求を「霊的な営み」として個人で励むことができる。
だが、意志が魂を介して破壊しに来たならば、
それ以後、彼は逃げられなくなる。
そして彼は、破壊されるまで、
その破壊の意義と、その素晴らしさを学ぶことになる。
そのときのみ、個の絶望は、喜びとなる。