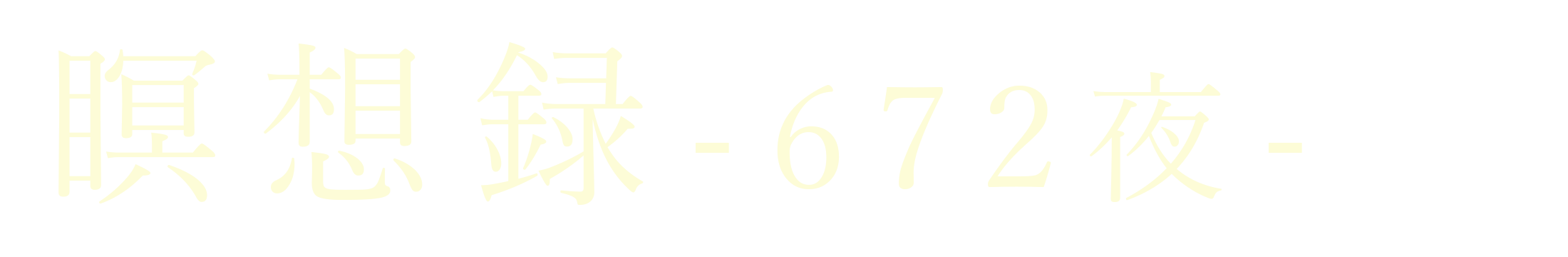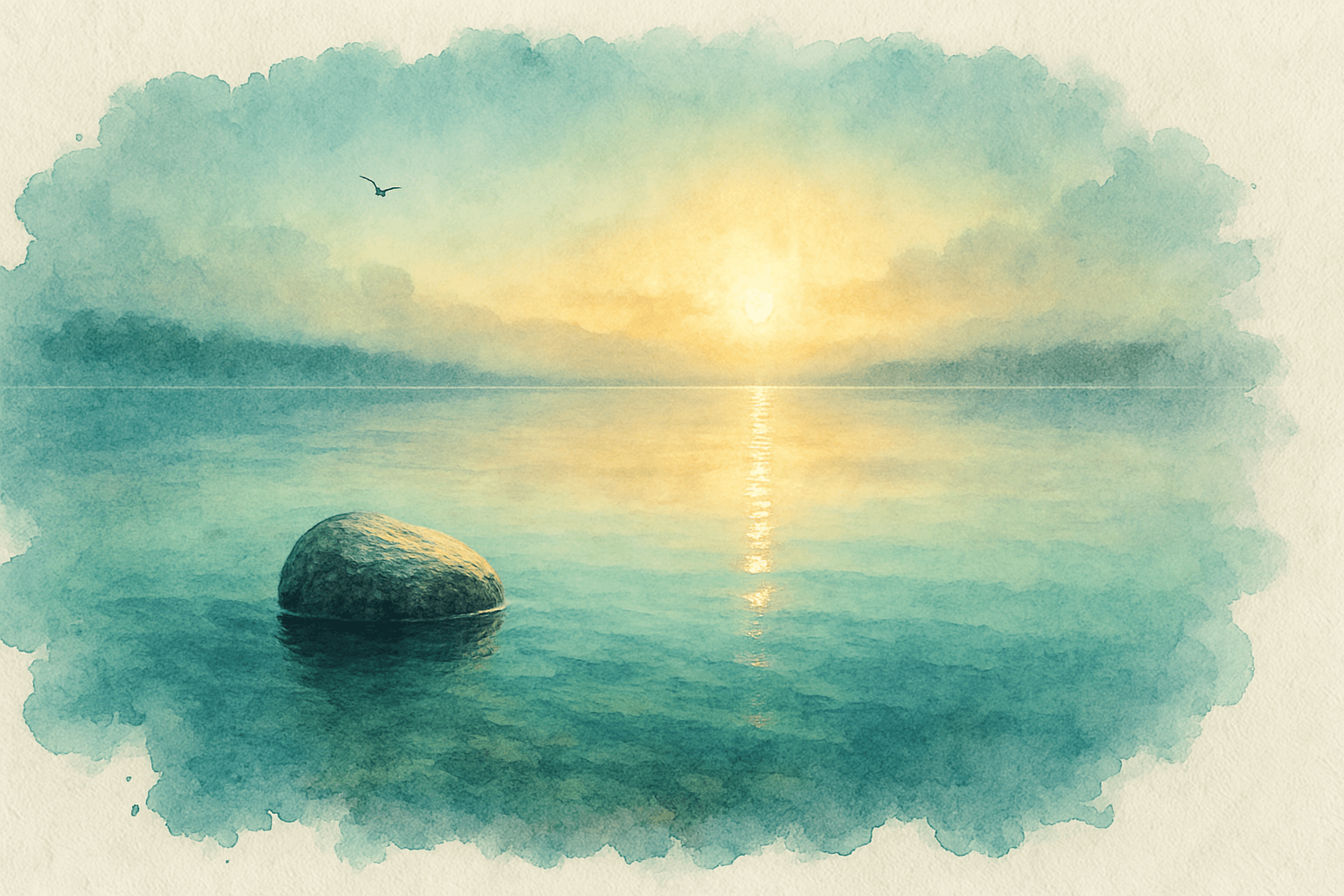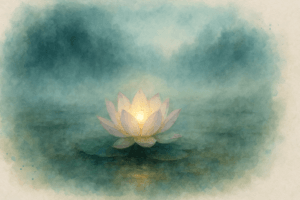われわれの多くは、聞いていない。
誰が聞き、誰が理解するのかを、自身に問うていない。
ゆえに、聞こうとしても、聞くことができない。
聞くことを阻害する個人を介入させている。
聞けないことは、語られる言葉の問題ではない。
心の深部に、話を遮る膜を持とうとするからだ。
それは、自己防衛のための自我の膜である。
知性の声、情緒のさざめき、
その両者が織りなす反応の網が、
語られたものの核心に触れる前に、それを包み、歪め、吸収する。
語られた言葉を
理解しようとした瞬間に、
それは既知に照合され、既知の分類棚に並べられる。
共鳴したと思ったとき、
実はただ、自分の内にある
快を伴う音が反響したにすぎない。
自身の快不快が、そのとき真偽の判断基準となる。
新しき教えは、既知の何ものにも属さない。
聞くとは、
思考の活動を沈めた知性が、
沈黙にのみ触れることのできる、より高位の知性と照会することだ。
それは、何かを考えることではなく、
知性と情緒の共鳴を基準とすることでもない。
そのような知的活動が生じることのない、沈黙の知性においてのみ、
真偽が見分けられる。
そのとき知性は、
何ひとつ介在させずに光を通す、澄明な点となる。
そのとき情緒は、
波も反射も起こさぬ、磨かれた静かな鏡面となる。
この純粋さによってのみ、聞くことは可能となる。
だが多くは、
語られた言葉ではなく、
語られた言葉によって喚起された、
自分自身の反応に耳を傾けている。
話を聞いているようでいて、
話に反応した自分を追っている。
そこにあるのは恐れだ。
「自分」が依拠してきた基盤が、今まさに崩れんとすることへの恐怖だ。
自我は、「基盤」を存続の条件とする。
そのため、自我は聞かないことを選ぶ。
これに気づけないことが無知である。
無知とは、光を拒む闇にも似て、
真理を拒む構造を自己の内に見ようとしないことである。
もし、光を見、聞こうとするならば、
人は崩されることを恐れない。
信念や熱狂といった、崩されうるものを所有して臨まない。
そのときのみ、
人間の知性は、
上と下との純粋な解説者、仲介者、架け橋となる。
信ずるものによって光を歪めないこと、
情緒の高ぶりによって識別を失わないこと、
自分の反応にしがみつかず、
沈黙が教える声なき教えに身をあずけること。
この、自由を求める個人の要求が不在であること、
その沈黙という自由の中に、
聞くことのできる知性は生まれる。
それが生まれるまで、
人は聞く用意ができていない。
彼が行うのは、知らぬうちに、
自我の基盤を肯定するための快不快との照合のみである。