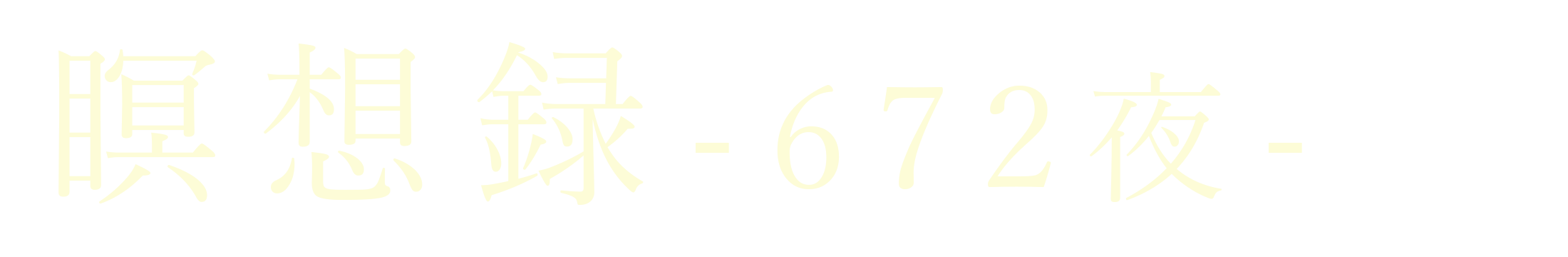瞑想中に何かを見たと言う人は多いが、それを見ている者が誰なのか、何なのか、その主体にのみ興味を持ち始めるのは、多少、瞑想の熟達が必要なのだろう。というのも、「見る者」と「見られるもの」がある場合、そこには苦痛があることに最初は気づかないからである。せいぜい、霊的な本を読んで、「私は誰か」と考える程度である。つまり、彼は「考えている」。考えることすら、考えることを可能にさせる主体なしには不可能である。すべてにおいてこれは適用できる。ラマナ・マハリシが、真我から離れて何も存在しないと言うのは、そういうことであって、真我とは何であるのかと、私から離れた別の何かとして考えたり想像したりしても意味がない。私が真我である。ならば、真我実現というが、私実現とは誰も言わない。私は実現されているではないか。私は、肉体が死のうが、在る。それは意識とは無関係である。だから、ニサルガダッタ・マハラジの本に、「意識に先立って」というタイトルがあるが、そういうことである。意識以前の私が真我だが、それは誰でも実現しているのではないか。
真我という概念に対する特殊なイメージを人は持つのだろう。イメージや想像や観念といったものに人は束縛され、その中に居住している。それゆえ生は恐怖である。例えば、死を人は恐れる。それはあまりに幼稚である。死んだり、消えたり、壊されたりするものが自分だと信じて生きることの脆さ、危うさに対して、何の切迫した危機感も持たずに過ごしてきたのかと、そういう人には言わねばならない。彼らの恐怖は、簡単に除去することが可能だから聞いてほしい。想像している私ではなく、その真の主観、真の主体、誰もが知っている私は死にうるだろうか。ここで問題なのは、「私」というものを通常の人間が理解できないことである。なぜなら、人々の「私」が概念や思考にすぎないことが分からず、そのようなものなしの、思考やマインドの活動に先立った、あるがままの私については理解しようとしないからである。というのも、真我を知ることを最も恐れているのは自我だからである。これを言い換えたとき、真我実現を妨害しているのは自我だと言うのである。つまり難しさは自作自演である。
ならば、「私は誰か」と己に問うことは正しいだろうか。誰とかではなく、すでに私は在るのではなかったか。あらゆるものに先立って、もしくは、あらゆるものの背後に、その前提や原因として、私は常に在るのではなかったか。人は夢を見ると言うが、見ている私がいたではないか。今もなお、読んでいる私がいるではないか。その上に、想念や気分や情緒が存在し、そちらに意識が同一化されているだけであって、「私」は常に存在している。無意識と呼ばれるものに関しては、脳の問題であり、目覚めと夢見の意識しか普通は記憶として保持できないだけであって、私が消えたわけではない。意識や知覚に関わらず、それ以前に、最初から存在する原初の私だけが重要であり、それは人々が見ているものとは逆方向の私であり、それは常に存在している私である。これを掴みきれるだろうか。
なぜなら、この「最初の私」さえ理解できれば、私が不滅の存在であることも同時に理解され、何に傷つけられることも、何かに影響を受けることも破壊されることもないことを知り、恐怖からは完全に自由になるからである。想念や情緒の汚染から浄化された純粋な意識へと瞑想は導くが、その意識が教えるのは意識以前の、最初から存在している私である。これはあまりにも単純すぎて分からないタイプの話である。分からないのは、人間の「分かる」が、考えて理解することを指しているからである。考える作用から自由でなくてはならない。つまりマインドを手放しても怖くないことを瞑想で知らねばならない。
瞑想を続けるならば、マインドはただ余計なもの、真理を覆い隠すだけのものでしかなくなり、関与する必要がないことが分かるだろう。つまり真の我々はマインドとは無関係であることを知り、一切の既知から孤立して自由であることを知るだろう。それは、知られるものがいずれも不要であるという意味であり、知ることを可能とさせている主体つまり私にだけ意識と関心が集中されることであり、それによって人は自身が自由であることを知る。肉体にも、あるいはカルマにも、自身が束縛されていない存在であることを理解する。これが真の無敵である。
人間は、無敵に憧れている。強さに憧れている。このような傾向は、有害なばかりに無知である。人々は、弱い自身と、強い誰かや何かという二分化を好んでいる。そうでなければ劇は続かないからである。しかし、その劇は恐怖を孕むのだということに、いつ人は気づくのであろうか。真のこの私自身は、いかなる分離(つまりマインド)からも自由であり、よって無恐怖であり、また無敵であり、向かうところ敵のない愛そのものであることを人々は知りたくないようだが、弱者を演じ疲れたならば、彼らもいつかは無敵なる己へ向かうだろう。
重要な話だからわかりやすい例を挙げる。漫画でも映画でもいいが、無敵の主人公が、真に無敵なら飽きてしまうため、常に難敵を登場させねば物語が続かないことは誰でも理解できるだろう。それと同じことをあなた方はしているのである。これが自作自演であることにいつ気づくであろうか。自我という物語が存続するために自ら創出し演出しているだけの自己劇化と自己演劇がいわゆる人生であることに誰が気づくであろうか。それは劇に疲れた者のみである。それは結局のところ、経験豊かな古い魂であるということになるのだろう。このような老いた魂は、物語を拒否する。物語が面白いとは思わない。物語は醜く、苦しく、悲しく、辛いものでしかないと感じる。だからそれよりも、ただ静かで在ることを好む。しかし平均的な魂は、睡眠のときだけ、この静けさへ帰る。そしていわゆる人生においては、ずっと真我を知らずに生涯を終える、というか生き切る。これは知性が発達している場合、心が壊れてもおかしくない地獄である。もっと賢くなり、したがって瞑想し、つまり安らかに沈黙し、そこに真の幸福と喜びを知らねばならない。物語は続かなくなるが、つまりそのあなたは死ぬが、真に良き者として復活するだろう。以上が果たして難しい話なのだろうか。私には、主人公が難敵なしには物語が不可能であるように、たえず自身で難しくしているだけに見えるのだが、この意味を理解し、難しさを編み出すマインドから撤退させる瞑想を愛する者が、どれだけいるであろうか。瞑想だけは、才能なしに誰でも習得できるというのに、結局まだ人類は、瞑想や沈黙より、物語や自分を今日も選択し、舞台に上がるようである。