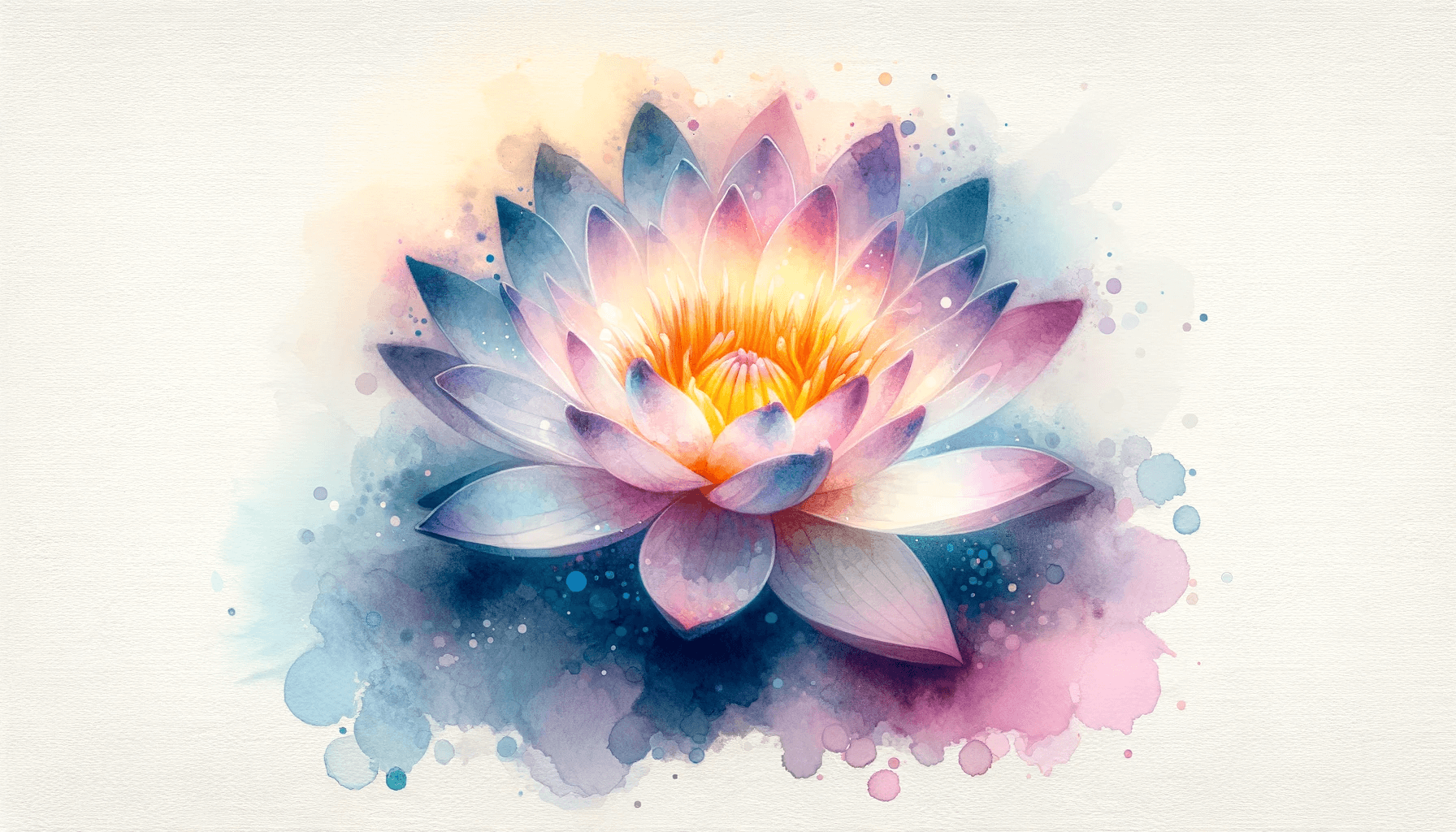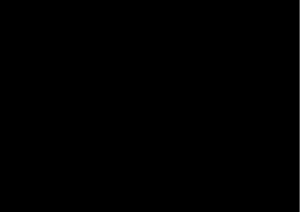客体とは、客体化の結果の仮相であり、ひとつのものを主体と客体に分割したマインドの罪であり、この罪に対する罰が分離という苦痛である。転生周期の終盤まで、人は経験を通して学ぶ必要があるため、主体と客体という分割はあえて利用される。やがて、人の魂が唯一なる魂に気づくようになり、自我(非自己)はおのれが魂(自己)において客体でしかないことを知ると同時に、すべての自我たち、すべての”客体たち”の中にも魂(自己)を見出し、外周から中心に至り、形態の背後に魂を見て、その魂の背後に生命を見るまでになり、先人の言葉である「蓮華の中の宝珠」という意味に入り、すべては私であるという唯一価値ある学びに到達する。したがって、「万物が神に従う時には、御子自身もまた、万物を従わせたそのかたに従うであろう。それは、神がすべての者にあって、すべてとなられるためである(コリント15-28)」。
人間のマインドは一を二に、二を多に分割することで、無数の他人という想念形態つまりイリュージョンに圧倒されてきた。多種多様にして数限りない他人と自らを比較するようになり、自身の無能に嘆いて卑屈になったり、他人の素晴らしさに嫉妬して憎しみや悲しみに屈従してきたりした。「ああなりたい」と人は言う。彼や彼女は、子供のときから「ああなりたい」を繰り返している。そして何かになったり、なれなかったりしてきたが、生は永遠に苦痛であった。何かになった者も何かになれなかった者も、その者とは常に「私」であった。これに気づくとき、何かになることが答えではないことを人は理解する。重要なのはすでに在る「私」であり、何かにならなくても良いということに人は驚き始める。なぜなら、そのような抵抗がなくなるとき、人は初めて幸福に包まれるからである。こうして、成るより在ることが栄光になる。外を見るのではなく、内を見るのでもなく、ただ在るようになる。このシンプルさが解放である。
主体に対する客体(その逆も然り)という想念の背後には常に恐怖がある。我々が波動を高め、徐々に意識が魂的になるにつれ、客体の知覚が即座に苦痛になる。したがって、客体化するマインドの活動停止が火急の要件になる。主体があるから客体があるという無知の構造に目が開かれ、客体ではなく主体へ、これまでとは「反対方向」に目が向くようになり、「私は誰か」と言い、見つけたときI AM THATと言い、それに安らぐときI AM THAT I AMと言えるようになる。この本質つまり真我はまた、すべての客体という表面ないしは想念の背後に存在する私である。客体の原因は想念であり、想念が客体化であり、このようなマインドの動きが静止するとき、生死の境目が判然となり、生命と死物、霊と物質の違いが明瞭となり、すべてが私であるという大調和が純粋な意識における事実となり、人は大至福に落ち着く。
客体の中に主体が在る。形態の中に生命がある。蓮華の中に宝珠がある。他人の中に私がいる。すべての背後に私が在る。主体と客体は乗り越えられる。分離は調和に席を譲る。衝突は融合に平和を知る。すべてが私であると同時に、私の中にすべてが存在し、その私とは……、その方については何も語ることのできないお方である。神や真我やどのような用語も、それ自体から我々を遠ざける。見えなくさせる。だから、概念の衣で神聖なる宝珠を覆い隠してはならない。真我という言葉に騙されてはならない。そのような概念や想念の中に、どのような形態にも内在する者がいる。それは私である。私が大調和である。主体でも客体でもない私がサマーディーである。「わたしは、よみがえりです。いのちです(ヨハネ11:25)」。
魂が低位マインドつまり具体化し客観化するマインドを支配したとき、いのちは明らかになるだろう。わたしは明らかになるだろう。わたしはいのちです。すべてはいのちです。すべてはわたしでありいのちです。これだけを未来の学校は教えるだろう。他人と競争させないだろう。比較しようにも他人がいないことを教えるだろう。誰も子供を苦しめないだろう。誰も、わたしを苦しめないだろう。わたしたちは、わたしを苦しめないだろう。