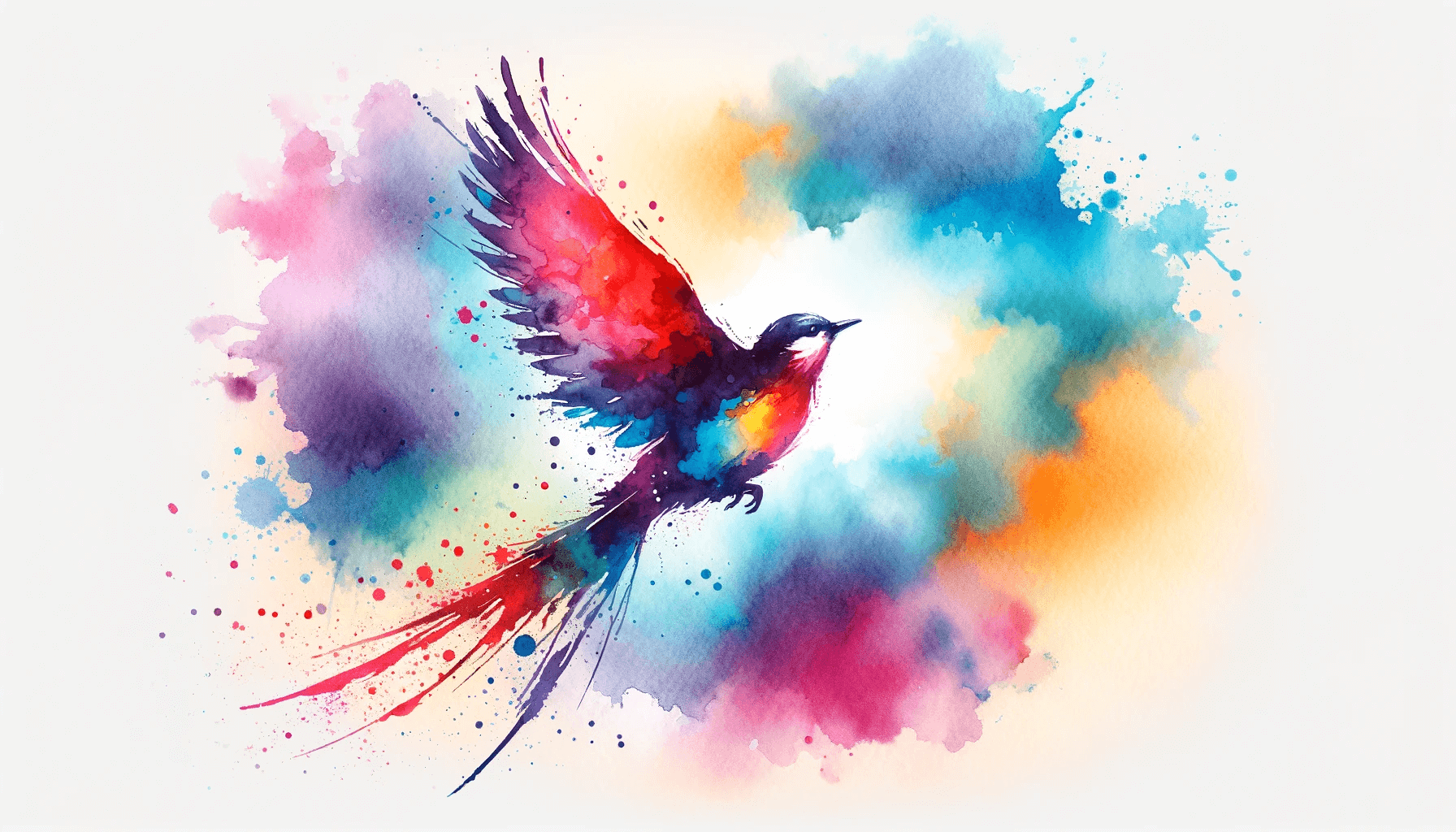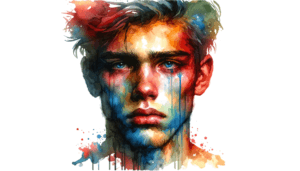法を守りつつ裁かれる者はいない。法に生きていながら、同時に罪を犯した者はおらず、よって罰せられた者もいない。真理の領域に冤罪はなく、天網は愛として無限にゆきわたり、現象の世界で起こる出来事にはいかなる偶然もありはしない。かつての行為の種を、われわれの名や形は刈り取るが、それに対しては法則内から、つまり法を破ることなく対処することで、さらなるカルマが生み出されることはなくなる。これを知ることが解脱である。というのも、真の瞑想において、われわれは完全に法則に入り、自我や感覚知覚のいかなる錯覚からも守護された本物の自由を知るからである。
…必然的にカルマの法則が形態と意識の関係を支配している。瞑想の過程は、正しく理解され実行されたとき、霊的人間の意識を三界のすべての形態から撤退させ、すべての感覚知覚から抽出する。このようにして純粋な瞑想の瞬間に、結果を生み出すカルマの様相から自由になる。一時的に彼は抽出され、完全に集中し三界とは何の関係も持たなくなった彼の思考は、外に向かう波動を全く発せず、どのような形態にも関与せず、どのような質料にも影響を与えなくなる。この集中した瞑想が習慣になり、生活において平常の日常的な態度になったとき、人はカルマの法則から解放される。
アリス・ベイリー「魂の光 」p.382
法学部とはなんだろうか。真の法学とは少なくとも方角を学ぶことである。外ではなく、「反対方向」である内の意味と意義を学ぶことである。外へ向かう自我という想念の内奥に、無法から守られた法則地帯を見つけることである。なぜなら、法則のみが調和だからである。人が作り上げた法律よりも大切な法を学ぶ必要があるのではないか。ここではカルマの法則について特に言及しているわけではない。法則に違反したとき、われわれは良きにつけ悪しきにつけカルマの網に捕らえられるのである。法則内にて法を犯さぬかぎり、どうしてカルマが存在できうるだろうか。
進学とは受験や合格を目指すものではなく、神学に進むことである。その神学とは法学である。なぜなら、神と法則は同義語だからである。自我がこれを知るとき合一するのである。法則に違反していた自我が、法則を完全に受容し、また法則に完全に受け入れられるとき、物質と霊は和解し、三界は超越されるのである。したがって瞑想は類まれなる法学部である。
世の法に習い、あるいは世の法を重んじつつ、誕生から死の合間に適用される法を知らないならば、何の意味があるだろうか。ふたたび別の形態で三界に戻ってくるだけである。何のために生きているのか、われわれは理解する必要がある。何の紛争に意識は巻き込まれており、またなぜ意識が形態をたえず携帯しているのか、その関係性と関係性に由来する葛藤を理解する必要がある。宗教も法律も、カルマや罪や罰の概念を正しく解釈できずにいる。つまり愛の意味が分からずにいる。真我が法則である。真我でないとき、法則に違反するのである。深く瞑想に入るならば、われわれは調和の何たるかを知り、本物の法と正義に守られるようになる。われわれが自我に生きるかぎり絶えず何かに飢え渇望しているが、この瞑想という法への籠城は、いかなる兵糧攻めも無効化する。なぜなら、法則そのものがいのちであり、充足だからである。したがって自我という外的な外敵は、城つまり白に守られた意識にはもはや太刀打ちできないことを悟り、勝手に諦めて去るのである。こうして新たな意識は、世界からの攻撃が止んだことを悟る。このように、法則に生きることが知恵であり、その結果が絶えることのない至福であり、その表現が愛と喜びであり、この意識は恐怖や苦悩から永遠に自由である。
自我に生きて、いまだかつて平和であったためしはない。自我と自我が友達になったり、結婚したり、一緒に仕事をしたりして、なぜ喧嘩や仲違いを繰り返すのだろうか。われわれの意識は、あまり重要ではないものを重要視しており、それゆえ本物に飢えている。偽物ばかり追い求めるから苦しいのである。存在しないものを存在すると認め、無価値なものに価値を与えるから悲しいのである。どれだけこの世で知的でも、情緒的で、欲求や恐れが何なのかを知らなかったり、苦痛が何なのかを見なかったりするならば、知性とは無縁である。小学生がなぜこれほど自殺せねばならないのか。学校は地獄なのだろうか。家庭や家族は名ばかりで実際は無慈悲なのだろうか。なぜ流行する歌の歌詞には高確率で愛が語られているのだろうか。誰も愛を知らないからである。外のどこに愛があるだろうか。分離した意識がどこに愛を見つけうるだろうか。一体性を知ることが愛である。法則を知ることが幸福である。調和を知ることが最高目的である。ならば、何と何が戦い、紛争をしているがゆえの不調和、自我意識なのだろうか。
誰もこれを教えられないが、誰もが自ら瞑想でこれを知ることができる。なぜなら、内にのみ本物の教師がいるからである。外の教師はいずれもせいぜい不正確だが悪意のない道案内程度であり、本物を知るためにはどのような教義や知識からも自由でなくてはならない。概念は到達を妨げることしかしない。どの教えも想念でしかない。想念ではなく、それらと関係のない、その背後の存在にわれわれは気づくことができるはずである。考えたり、頭を使ったらそれは分からなくなる。感じることが重要である。一時間の瞑想で、一度は幸福な意識状態を知覚するかもしれない。その感覚の源をもっと辿りゆかねばならない。それは決して努力ではない。そこには決して力みはありえない。なぜなら、源とはわたしそのものだからである。愛や至福や喜びは、わたしだからである。こうして人は、真我という法則に参入できるようになる。そして何が意識を三界へ縛りつけてきたかを理解する。事はシンプルかつ明瞭になる。視力は戻り、行為は存在に席を譲る。残りのカルマは知的に精算されるようになり、立つ鳥跡を濁さぬようになる。つまり新たなカルマを残さぬようになる。これが法学である。